クレジットカード現金化をするために現金化業者を利用したいけど、色々不安だから利用するなら現金化優良店を利用したいと思いますよね。
しかし、「優良店ってどうやって選べばいいの?」と、思っている方がほとんどかと思います。
結論から言うと2024年4月24日時点で、最も優良なのは、「タイムリー」となっています。理由:高換金率・最短5分で入金
 メディア編集部
メディア編集部
この記事では優良な現金化業者の選び方や安全に現金化をするためのポイントはもちろん、最新の優良店ランキングも発表しています!
ホントの話のお約束
当サイト(クレジットカード現金化ホントの話)では、以下項目を徹底しています。
- 中立な立場で現金化業者を比較します。
- 悪質(詐欺)サイトは掲載しません。
- 現金化利用者の口コミを大事にします。
- 編集部でも実際に利用して安全か確認します。
- 利用者に有益な情報(1円でも高く)を提供します。
なぜホントの話が信頼できるのか?
「ホントの話」は、
現金化業界の専門家が提供する情報実際に現金化業者を運営であり、
100社以上の現金化業者を比較し、編集部自身も実際に利用しているため、
経験・体験に基づいた情報で信頼性が高いと言えます。
また、編集部の運営体制が整っているため、正確で信頼性の高い情報を提供できるように努めています。
ただし、情報を利用する際には、自分自身でも情報を確認し、判断することが重要です。
この記事で分かること
著者情報
「クレジットカード現金化ホントの話」のメディア編集部、橘かりんです。ホントの話ではこれまで様々な現金化を実際に経験してきました。クレカ現金化のことなら全て知っているので、騙されたくないあなたに最新で嘘のないのホントの話を発信していきます。
クレジットカード現金化おすすめ優良店ランキング

 メディア編集部
メディア編集部
おすすめのクレジットカード現金化優良店ランキングを発表していきたいと思います。なお、ランキングの最終更新日は「2024年4月24日」となっております。
1位:タイムリー
| 最大換金率 |
98.6% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
8時~20時(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://cardtimely.com/ |
タイムリーの特徴
タイムリーの最大の特徴としては、業界内最高レベルのキャッシュバック率を誇っている点があげられます。
他社よりも換金率が1%でも低い場合はその旨を伝えることができますので、より高い換金率を重視する方におすすめです。
また、急に現金が必要になった場合にも、スピーディーな取引ができるのもうれしいポイントです。
年中無休のため、平日はもちろん土日祝でも24時間いつでも即日対応可能となっていて、なんと最短で5分で振り込みが行われます。
全てのクレジットカードで現金化が可能で、審査や来店などは一切必要なく、収入証明も不要ですので気軽に利用することができます。
こういったクレジットカード現金化について不安に思う方もいらっしゃるかと思いますが、タイムリーでは個人情報の取り扱いやカードセキュリティについて万全の体制を整えているうえにカードによる事故やクレームゼロという実績もありますので、安心して利用することができます。
タイムリーの口コミ
担当者の方が丁寧な対応をしてくださったので、安心できました。何よりも振り込みがスピーディーで驚きました。審査もないのでとても使いやすかったです。他社で審査落ちしましたが、こちらでは換金することができましたのでありがたかったです。
資金繰りの時間が捻出できず、クレジットカードの現金化業者を利用しようと考えました。ちょうどキャンペーンがやっていたのでお得だと感じ、問い合わせて急いでいることを話しました。きちんと当日に振り込まれ、感謝しています。
初めての利用でしたがスタッフさんの対応がよく、入金時間や連絡の取れる時間を確認してくださったので、滞りなく現金化をすることができました。初回の特典があり、換金率にも満足していますので、また機会があればこちらを利用したいと思います。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
2位:ブリッジ
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
平日9:00~19:30
土10:00~17:30
日祝10:00~17:30 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://bri-dge.net/ |
ブリッジの特徴
ブリッジは91~98%保証されている優良現金化業者です。
10年以上の実績があり、これまでカード事故ゼロ。クレジットカードの現金化に不安がある初心者の方でも安心して利用することができます。特に男性利用者は優遇されており、換金率が3%アップするうれしい特典つき。キャンペーンも定期的に行われているので、お得に現金化したい方にもピッタリです。
1万円からの少額利用も可能なので、ちょっとした現金調達にも重宝します。
ブリッジの口コミ
ブリッジは信頼性抜群!創業10年以上でカードトラブル0件の実績が安心です。スピーディーな振込も嬉しいポイントです。
換金率保証があったので安心して利用できました。10日間の補償があるので、他の業者より損しないとおもいます。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
3位:いますぐクレジット
| 最大換金率 |
99.5% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
9:00~21:00(土日祝も営業) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://imasugu-c.net/ |
いますぐクレジットの特徴
いますぐクレジットは最大換金率99.5%という驚異的な数字を実現させているクレジットカード現金化業者です。
これは一度に100万円以上の現金化を行った場合に適用される最大換金率であるため、一般の利用者にはあまり関係のない数字に思えるかも知れません。
しかし、いますぐクレジットは1万円から10万円という一般利用者の割合がもっとも大きいであろう利用価格帯での換金率も91%という非常に高い数字になっています。
そこから段階的に換金率が上昇して99.5%まで到達するため、どの価格帯で利用するとしても、いますぐクレジットの高換金率設定の恩恵を受けることは十分に可能になるでしょう。
ただし換金率は申し込み時の状況や複数の条件によっても変動するため、詳しくはいますぐクレジットのスタッフに直接確認することも大切です。
いますぐクレジットの口コミ
いますぐクレジットで20万円ほどのクレジットカード現金化をしてもらいました。換金率の表だと10万から30万の利用で93%となっていたので10万寄りの換金率にされてしまうかなと思っていたのですが、ちゃんと20万円で計算してもらうことができて助かりました。
いますぐクレジットの換金率はホームページの記載通りにはならない感じがしますね。ただ、それはどの現金化業者も大差ないのでいますぐクレジットが特別悪いというわけでもないです。むしろ平均よりはちょっと上くらいにはなるかなと
申し込みから現金振り込みまでの時間はかなり早い方だと思います。初回の申し込みではこちらが結構色々と質問をしてしまったこともあって2時間くらいかかりましたが、しっかり即日振り込みになったので満足しています
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
4位:GENKINKA ITORI
| 最大換金率 |
99.5% |
| 入金スピード |
新規最短15分 |
| 営業時間 |
24時間申込可能 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://genkin-kaitori.org/ |
GENKINKA ITORIの特徴
GENKINKA ITORIは安全対策を徹底しているクレジットカード・プリペイドカードなどの現金化サービスです。
創業してから19年も運営していて、一度も換金率についてのクレームやクレジットカードのトラブルについての報告がないという実績があります。
GENKINKA ITORIでは手数料については振込手数料、商品送料、システム手数料、キャンセル料がかからないと明記していて安心です。
セキュリティ対策を徹底しているため、個人情報の漏洩リスクも低く、誰にも知られずに利用できるのが特徴です。
また、GENKINKA ITORIは利便性も重視していて、土日祝日も含めて営業し、電話受付も夜10時まで対応しています。
初めての人でも最短15分、リピーターなら最短5分での振込をしているスピード対応のサービスなので、便利で使いやすいのがGENKINKA ITORIの魅力です。
GENKINKA ITORIの口コミ
GENKINKA ITORIはスピーディーで快適でした。本人確認のときにだけ少し手間がかかりましたが、その後の対応は早くてATMに行くまでの間にもう振り込まれていました。2回目以降はもっと時間がかからなくなるらしいです。お金に困ることは多いので今後もうまく使っていきたいです。
GENKINKA ITORIを使う決断をして本当に正解でした。先月から怪我で働けず、休職していて収入がなく、医療費もかかっていて生活が苦しい状況でした。もう1週間で退院できるというところで30万円も手に入れることができ、本当に助かっています。復職できればすぐに払えるようになるので、きちんと体を治して頑張ります。
日曜日も営業していて助かりました。土日連続の飲み会で気づいたら財布にお札がなく、飲み会の場で友人にこっそりお金を借りないとかなと思っていました。ふとGENKINKA ITORIについて思い出して申し込んでみたら、飲み会中にきちんと振り込まれていました。ちょっとトイレが多いなと言われるくらいで済んで良かったです。
詳細を見る無料お見積りはこちら
新規最短15分でお振込み
5位:いいねクレジット
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
年中無休
24時間申込可能 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://iine.life/ |
いいねクレジットの特徴
いいねクレジットには様々な特徴がありますが、やはり誰にも知られることなく現金化ができることでしょう。
実はこういった業者の中には利用をした際に登録した住所に明細が届いてしまうことがあるのです。
これが届けばいくら内緒にしていても家族などに知られて場合によってはトラブルに発展してしまいます。
ところがいいねクレジットはそもそもペーパーレス取引なので明細書の送付が行われないのです。
しかも貸金業ではないため、勤務先への在籍確認がないのも有難く職場の上司や同僚にも隠して利用できます。
いいねクレジットの口コミ
電話だけでなくWebでの申し込みができるのが嬉しかったです。ホームページでは最短5分で完了ということでしたが、初めての私でも時間をかけることなく申し込みができました。
以前他の業者を利用していたのですが、手数料を取られて少し損をしていました。でもいいねクレジットさんは手数料がかからないので、逆に申し訳ない気持ちになってしまいます。
とにかく在籍確認がないのは本当に助かります。あまり会社に知られたくないので、本人確認はあっても在籍確認がないのは軽い気持ちで利用することができます。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
6位:現金化ベスト
| 最大換金率 |
98.8% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
9時~19時30(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://genkinkabest.com/ |
現金化ベストの特徴
現金化ベストは、「換金率&安全性NO.1宣言」を掲げているおすすめサイトです。
創業以来カードトラブルなし、換金率保証サービスなど、ユーザーファーストな現金化ベストは、リピーターの方も多数。たくさんの方から支持されています。
男性の方は自動的に男性限定プランが適用されるなど、充実したキャンペーンも魅力的ですね。換金率は最大98.8%と、業界TOPクラスです。
他社よりも良い条件で現金化したい方は、是非とも現金化ベストをご利用ください。
現金化ベストの口コミ
友人から紹介されて利用してみたけど、満足の換金率で入金も即日。いい業者だなと感じました。紹介キャンペーン適用で友人にもお小遣いが入ったみたいだし、winwinです。
少額からでも利用可能なところはかなり大きい。振込スピードもめちゃくちゃ速いし、ここ数か月は毎月のようにお世話になってます笑
男性限定のキャンペーンをやっている業者はあまり聞いた事がないね。すごく良いサービスだと思う。現金化ベストはキャンペーンが豊富だし、また利用すると思います。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
7位:ソニックマネー
| 最大換金率 |
99.2% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
9時~20時(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://0120504030.com/ |
ソニックマネーの特徴
ソニックマネー特有のキャンペーンやサービスが展開されているという点が挙げられます。
特にお得なのが、他の現金化業者からの乗り換えで換金率を優遇してもらえるキャンペーンです。
他社の換金率に不満があった場合は、ソニックマネーを利用することでよりお得に現金化サービスを利用することが可能になります。
また、全ての金融機関とカード会社に対応しているという点も、ソニックマネーの大きな強みです。
利用する際に、自分の利用しているサービスが対応しているかどうかの心配をする必要がありませんので、利便性の面でも非常に優れた現金化業者であると言えるでしょう。
ソニックマネーの口コミ
Webフォームで申し込みをしてから、わずか30分以内に入金してもらえたので、全くストレスがかからず利用できました。実際に利用する面でのデメリットはほぼ感じませんでしたが、営業時間が20時までなのが、やや難があるかなという印象もあります。できれば23時くらいまでは営業していただけると助かりますね。
スタッフ対応が親身なのはもちろん、非常に効率的だった印象があります。以前利用した他の業者に比べ、利用説明がやや簡略的な印象もありましたが、必要な説明は簡潔にしてくれるので不安はありませんでした。寧ろ長々とあまり身の無い説明をされるよりも良い印象でしたね。
きちんと教育がされているなという感想を持ちました。
過去にカードトラブルが発生したという話も聞かないので、安心して利用できる業者だと思います。特に初めて利用される方は、スタッフ対応が気になるポイントであると思いますが、実際に利用した感じだと非常に口調も穏やかな対応だったので、初心者の方にもおすすめの業者だと思います。私の場合は急な出費での急ぎの要件だったのですが、それでも丁寧な対応かつ迅速な即日入金で、非常に助かりました。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
8位:プライムウォレット
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短10分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://prime-wallet.com/ |
プライムウォレットの特徴
クレジットカード現金化業者として人気のお店であるプライムウォレットは、最大還元率が98%と圧倒的に高いことやサービス内容が丁寧なことで人気があります。
特にスタッフの対応が丁寧という口コミが多く、そのため初心者さんでも安心して使えるクレジットカード現金化業者としておすすめです。
キャッシングやローンにある審査はプライムウォレットでは必要ないですし、手続きにあたっては本人確認書類以外のものが必要ないで素早い手続きをすることが可能です。
最短で10分という素早い現金化ができますし、プライムウォレットは土日祝日対応をしており24時間受け付けをしているので忙しい人でも申し込むことができます。
クレジットカードのキャッシング枠を利用する形式になっているのですが、こちらの支払いは一括でもリボ払いでも大丈夫となっているので自分に合わせたものを選ぶことが可能です。
プライムウォレットはクレジットカード現金化に対する実績がよくカード事故も発生していないので、安全なお店としておすすめです。
プライムウォレットの口コミ
使い道を問わないで現金化することができると聞いたのでプライムウォレットに申し込みをしました。主に娯楽費として使う目的だったのですが、手続きに関しては特に問題なく進みましたし、還元率もかなり高めだったので満足しました。
安全なクレジットカード現金化業者として紹介されたのですが、実際に使ってみるとスタッフさんの対応が丁寧でとてもよかったです。初めての利用だったので不安な点もあったのですが、きちんと質問に返答してくれたのも嬉しかったです。
年末急に現金が必要になったのでプライムウォレットを使いました。年末の祝日ということもありかなり忙しい時だったのですが、即日すぐに現金が振り込まれていたので助かりました。特別な審査もないので気軽に申し込めるのは良い点だと思います。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短10分でお振込み
9位:インパクト
| 最大換金率 |
98.6% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://aichi-pump.jp/ |
インパクトの特徴
即日現金振込で最短で5分で利用可能。最大換金率は98.6%となっています。
但し、あくまで最大、ではありますから、その点が注意したほうが良いところです。
なお新規申し込みで2%換金率をアップしてくれます。
支払いなどに関しても分割を含めリボ払いなどにも対応していますから、自分のペースで返済していくことも可能なように配慮されています。
来店審査なし、収入証明書などの用紙などの提出も必要ありませんので手軽に利用することが可能になっています。
そして、カード停止トラブルの件数が0というのも特徴的なところであると言えるでしょう。
最低還元率保証宣言ということで他社よりも1%でも低かった場合に相談すると可能な限りということではありますが対応してもらうことができるようになっています。
スマホからの申し込みが簡単にできるわけであり、物凄く使いやすいようになっています。
第三者に利用したことが発覚することもないです。
インパクトの口コミ
どうしてもお金が必要であり、利用することにしました。すぐに対応してもらうことができましたし、換金率に関しても満足いく水準でお願いすることができました。難しい手続きなどもなく、説明もしっかりとしてくれたので不安なこともなかったです。
他で安い所があったら相談にも乗ってくれるという点が気に入ってとりあえず話してみることにしました。幸いにしてカードが利用できたので監禁をお願いすることができましたし最短5分というのもさすがに5分ではなかったですがかなり早かったので助かりました。誰にもバレることなく利用できました。
突然の支払いに困っていたのですがすぐに現金化させてもらうことができましたので助かりました。即日でやってもらえましたし、換金率に関しては予想と比較してということを特にあったわけではないのですが思った以上に良かったです。また機会があれば利用したいと思えるよいところでした。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
10位:ラストチェンジ
| 最大換金率 |
99% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://lastchange.net/ |
ラストチェンジの特徴
ラストチェンジは、最大換金率99%となっています。また、他社より低ければそれより1%以上高く換金してもらえるキャンペーンをしているため、他社には換金率が負けないようになっています。
カード事故0件となっており、安心して依頼できるクレジットカード現金化業者です。担当制のスタッフになっていますので、話が途中でわからなくなるようなこともありません。
初心者でわからないことを聞く人や、換金率を高くしたいリピーターにとっても、顧客満足度も100%となっています。
身分証明書の提示は、一枚でOKとなっていて、複数は必要がありません。
そのため換金までのスピードを速くしているというメリットもあり、最短で5分以内で換金できます。
見積もりや相談だけの問い合わせも受け付けているため、不明な点が多くうまく現金化できるかを心配している人も、自分がよく理解できて納得してから、クレジットカード現金化を依頼することができます。
ラストチェンジの口コミ
今までクレジットカード現金化を他の業者でしたことがあったけれど、ラストチェンジは、その中で一番高い換金率で現金化することができました。お金に困っていて少しでも多く現金化したかったので、とても助かりました。
スタッフの対応がよくて、何度か問合せをしましたが、すべて丁寧で納得できる回答でした。見積もりも初めて取りましたが、実際の現金化の金額を知ることができて、理解してから現金化の依頼をすることができました。
最短3分という記載があり、本当にそんなに速いのかな、と思っていましたが実際にも10分くらいで入金がありました。こんなに早く現金を手に入れることができると思わなかったので、びっくりしました。また利用すると思います。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
11位:スピードペイ
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短10分 |
| 営業時間 |
24時間営業 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://speed-pays.com/ |
スピードペイの特徴
スピードペイは、24時間メールフォームやLINEで見積もりと申し込みを受付しています。
電話の受付時間は朝9時から夜8時となっていて、フリーダイヤルを設置しているため無料です。
実際に対応して振込をするためには、電話確認が必須なため、電話の受付時間の入金になっています。
他社との見積もりを比較した時に、1%でも低いようなら相談できるようになっているため、高い換金率を実現しています。現金化したい金額が増えるほど、換金率は高くなる仕組みです。
スピードペイの稼働している時間や銀行の口座などの条件がそろえば、最短10分での入金ができます。
キャッシュバック方式での現金化方法のため、ショッピング枠での買い物をしたことをスピードペイが確認できればすぐに入金できる流れとなります。
来店不要、審査不要で本人名義のクレジットカードのショッピング枠の残金があれば現金化できます。
カードリスクゼロ、事故等ありませんので、安心して現金化依頼ができる業者です。
スピードペイの口コミ
平日の昼間に依頼をしたら、すぐに電話での確認の連絡があって入金も1時間くらいでありました。LINEで連絡できるため便利です。思ったより早かったので良かったです。
現金化業者が複数あるためどこにするか迷いましたが、できるだけ換金率を良くしたく他社との見積もりも可能だったので、スピードペイにしました。換金率はどこよりも高かったです。
仕組みや換金率などわからないことがあり、何度かメールや電話で問い合わせをしましたが、親切で丁寧に説明をしてもらいました。現金化は不安でしたが説明の通り振込があったので良かったです。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
12位:あんしんクレジット
| 最大換金率 |
98%~ |
| 入金スピード |
最短10分 |
| 営業時間 |
9:00~20:00(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://anshincredit.net/ |
あんしんクレジットの特徴
あんしんクレジットは、平成12年に設立された20年以上も歴史を持つ老舗の現金化業者ですので、実績も豊富です。
かなり高水準のサービスを提供する現金化業者の1つでおすすめです。
というのも、初めての利用者に対しても平均振込スピードは15分、また、気になる換金率も91%~98%という高水準をマークしており、業界トップクラスです。
ただし、あんしんクレジットはやはり優良店なだけあって電話がつながらなかったりと、混雑していることがよくあります。
ですから、できる限り余裕をもって連絡しておくことをおすすめします。
あんしんクレジットの口コミ
口コミとかをチェックしてみると悪質業者なんて書かれているようでしたが、実際にあんしんクレジットを利用したら悪質という感じは一切しませんでした。換金率も断然他社よりもあんしんクレジットの方がすごく良かったですし、スタッフの対応もスピーディで私は満足しています
あんしんクレジット使ってみた所、8万円の利用額に対して換金率は81%でした。以前利用していた現金化業者と比べたらかなり親切でした。無料相談や見積もりをしてくれる業者って実はなかなかないのですよね…だけど、あんしんクレジットはやってくれたので安全業者だと思います
最短10分で振り込んでくれるとあったので利用したのに、どうやらオンライン決済してから振込までの時間が10分だったみたいです。なんか騙された感じがしました。それに、還元率リストが載っていないのも何だか不安を感じたので、あまりおすすめしません
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短10分でお振込み
13位:どんなときも。クレジット
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9:00~18:00(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://donnatokimo-c.com/ |
どんなときも。クレジットの特徴
「利用料・手数料無料」を掲げるどんなときも。クレジットは、優良店を探している方、換金率の高さを狙う方には見逃せない現金化業者でしょう。
どんなときも。クレジットは、弁護士との協議調整を行い、どんなときも。クレジットにとっても、そして、現金化利用者にとっても違法性のない安全な取引ができるように取り組んでいます。
平均換金率は80%以上となっており、具体的な例を挙げると、8万円の現金化に対して82%程度の換金率が適用されています。
ただし、ちょっとデメリットとなるのが、営業時間です。
土日祝日に営業はしていますが、9:00~18:00の対応となるため、いくらモアタイムを採用しているとは言え、この営業時間内に申し込まないと、翌日以降の振り込みとなるので、ちょっと厳しいかもしれません。
どんなときも。クレジットの口コミ
実質的な手数料が以前利用していた他社よりかなり低かったようで、クレジットカード現金化をしたら、3万円と利用額に対して換金率は81%だったので、満足して利用できました。間違いなくどんなときも。クレジットは優良店だと思います。おすすめです
どうしても現金が必要なのにない、そんな時にはどんなときも。クレジットにお世話になっています。どこの現金化業者よりも高い換金率でクレジットカード現金化を行ってくれるのでおすすめです。何度か利用していますが、いつも換金率は82~84%と満足のいくものですし、スタッフの対応の良さも好感が持てます
どんなときもクレジットを初めて利用したのですが、10分で入金されるなんて嘘でした。結局1時間くらいかかったので、振り込まれないのではないか、詐欺業者を利用してしまったのではないかとかなり焦りました。どうやら最短時間はリピーターに適用されるもののようですが、だったら最初から書いておいてほしいです
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
14位:キャッシュライン
| 最大換金率 |
98.8% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
記載なし |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://cash-line.net/ |
キャッシュラインの特徴
キャッシュラインは大手企業が運営している由緒正しいクレジットカード現金化業者です。
だからこそ高い換金率で人気がありますし、応対するスタッフはみな丁寧です。
クレジットカード現金化についてしっかりとした知識があるプロフェッショナルばかりなので安心して利用することができるでしょう。
またクレジットカード現金化業界で初となるLINEで相談が出来るシステムの先駆けでもあります。
こうした企業努力の結果、クレジットカード現金化をしたことがない方もすでに他の業者で利用した経験があった方もみんなファンになるのです。
キャッシュラインの換金率はなんと最高で98.8%であり、これはクレジットカード現金化業者の中でも文句なくトップクラスです。
たくさんの金額を利用した時だけではなくちょっとだけの決済時でもしっかりと現金化してくれるのです。
さらにキャッシュラインではスピード対応も自慢です。最短5分で指定した口座に振り込んでもらうことができるのです。
金融機関が営業を終わってしまう15時を過ぎていても、土日の場合にもしっかりと対応してくれるのも嬉しいですね。
キャッシュラインの口コミ
これまでいろいろなクレジットカード現金化業者を利用してきましたが、どれもいまいち満足できずにいました。しかし今回初めてキャッシュラインを利用して「これだ!」と思える業者に巡り会えたと思います。これからはキャッシュライン一筋で行きます。
急に現金が必要になったのに給料日が遠くて止むを得ず利用しました。信用情報機関に履歴が登録されないキャッシュラインはとって最高のサービスでした。すぐに振り込んでもらうことができたので不安なく取引ができました。
クレジットカードの現金化は難しいと思っていたのですが、思ったよりも簡単に現金を手にすることができました。キャッシュラインの担当者さんはみんな優しくて、こちらの素人丸出しの質問にもしっかりと答えてくれました。ありがとうございます。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
15位:セーフティーサポート
| 最大換金率 |
98.9% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://safetysupport.net/ |
セーフティーサポートの特徴
2001年4月の創業以来、20年を超える実績があるセーフティサポートは、これまで60,000人以上もの現金化相談を受けてきた業界の老舗です。
高い換金率とわかりやすい説明、最短5分でスピーディーに行われる入金処理は利用者からの信頼が厚く、多くのリピーターを抱えています。
年中無休で24時間365日いつでも申し込みでき、サポート体制も万全に整えられているのが特徴。
わからないことがあればすぐに解消できますし、急ぎの場合には、9時から20時までの営業時間内に直接電話をかけて手続きを進めることも可能です。
なお、平日15時以降、土日、祝日の申し込みに関してもゆうちょ、楽天、ジャパンネット銀行のいずれかの口座を振り込み先に指定することで、即日入金されます。
セーフティサポートの魅力は、利用者にとって明朗な決済が約束されている点にもあり、詳細がわからない手数料が一切発生しないのが安心です。
電話での相談の際には適用される換金率と正確な入金額が説明され、承諾した金額がそのまま振り込まれます。
セーフティサポートの口コミ
最初は現金化業者なんて怪しいし審査もいらないなんて怖いなと思ったのですが、どういったシステムで現金を振り込んでもらえるのか、わからないことを1から教えてもらえて納得できました。現金化のイメージががらりと変わったのは、こちらの親切なスタッフのおかげです。
何度か利用していますが、いつも振り込みが早いです。さすがに最短5分とはいきませんが、15分から30分くらいで入金の連絡が来るので、急いでいる時にはとても助かっています。事前にどのくらいかかるか聞いておくと、大体その通りに手続きしてくれるので安心です。
換金率はこうなって振り込まれる現金はこうですと、正確に教えてくれるので信頼しています。悪質なところだと、高換金率で釣って後からあれこれと理由をつけて諸費用を差し引く、なんてところもありますが、ここならそんな手数料は一切ないので誠実な業者さんです。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
16位:ひまわりギフト
| 最大換金率 |
96% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://himawarigift.net/ |
ひまわりギフトの特徴
ひまわりギフトは、クレジットカード現金化業者の中でも創業13年という長い歴史を誇る業者です。VISA、マスターカード、JCB、AMEX、ダイナーズクラブの5ブランドに対応しています。
ひまわりギフトは、取引終了後、入金されるまで最短5分というスピーディーな対応が特徴です。初めて利用する方でも、申し込みを始めて20分から30分ほどで振り込みが完了すると思われます。
手続きも全てネットで完結するので、日本全国どこに住んでいても利用できます。
また、自分に合った支払い方法を選べるのも、ひまわりギフトの特徴です。
カードのショッピング枠を利用して換金した費用は、現金化した後にカード会社へ返済する必要があります。その返済方法も、カード会社で設定している一括払い・分割払い・リボ払いから選ぶことができます。
換金率は最大96%と、業界内でも高い水準を誇っており、毎月15日は「ひまわりの日」として、換金率がさらに3%アップします。
ひまわりギフトの口コミ
生活費がどうしても足りなくなってしまい、親にも頼ることができなくて困っていました。そんな時にネットで調べてひまわりギフトのことを知り、対応の早さに定評があると言われていたので利用しました。実際に使ってみると、言われていた通り1時間ほどで振り込みがされたので驚きました!
はじめてクレジットカードでの現金化を利用したので不安でしたが、スタッフの方がとても丁寧に対応してくれて、説明も分かりやすかったので安心して手続きすることが出来ました。換金率UPなどのキャンペーン情報も電話やメールで教えてもらえるので有難いです。
急にお金が必要となったので利用しました。現金化のサービスをネットで調べて、換金率が高いとあったひまわりギフトに決めました。利用してみたら、実際に96%で換金できたので嬉しかったです。返済方法も一括払いか分割払いかを選ぶことが出来たのでよかったです。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
17位:トラストキャッシュ
| 最大換金率 |
99.5% |
| 入金スピード |
最短15分 |
| 営業時間 |
9:00~20:00
WEB申込 24時間365日対応 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://trust-cash.net/ |
トラストキャッシュの特徴
トラストキャッシュはクレジットカード現金化の初心者も気軽に利用できるサービスです。
電話でもWEBでも簡単に申し込めるだけでなく、ユーザーサポート体制が整っていてガイドに従うだけで現金化ができます。
初心者が不安になりがちな個人情報の漏えいやカード事故などもゼロで、秘密で現金を手に入れることが可能です。
トラストキャッシュでは換金率も重視していて、93.0%~99.5%という業界でもまれに見るクラスの高さになっています。
ショッピング枠が無駄にせずに、うまく現金を手に入れたい人に向いているクレジットカード現金化業者です。
対応スピードも速くて申し込みから最短15分、手続き完了から最短3分で振り込んでもらえるのも魅力です。
トラストキャッシュの口コミ
トラストキャッシュは2回目になると振込スピードが速くなるのでおすすめです。1回目に比べて手続きが少なくて簡単になります。私のように細々とした出費があったときに、その都度使いたい人に向いていると思いました。
トラストキャッシュを使ってみて、振り込みはそんなに早くないかなと思いました。でも、換金率が高いのでトータルバランスとしては優良だと思います。初めての人でも30分くらいあれば振り込んでもらえます。
希望時間に電話をもらえてよかったです。仕事の昼休み中に家賃の支払いができないことに気付いてWEB申し込みをして、夕方の連絡をお願いしたら希望通りに電話がかかってきました。おかげさまで即日で現金化できて難を乗り越えられました。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短15分でお振込み
18位:ゼロスタイル
| 最大換金率 |
99.2% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9:00~20:00(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://zero-style.org/ |
ゼロスタイルの特徴
現金化ユーザーが安心して利用できるように手数料の明瞭化と親切接客に努めているのが、ゼロスタイルです。
ホームページを見ていただくとおわかりのように、とにかく内容が充実していてわざわざ問い合わせなくてもホームページがすべて解決してくれる内容となっています。
振込手数料や配送料がかからないので、利用者への負担が少ないことはもちろん、振込時間は平均して20~50分とスピーディ、さらには平均して83%前後を誇る換金率の高さもおすすめのポイントです。
また、ゼロスタイルでは利用前に相談や見積もりを行うという、まさに優良店スタイルをとっているので、ぜひご活用ください。
現金化に詳しいスタッフが丁寧にあなたをサポートしてくれます。
ゼロスタイルの口コミ
5万円現金化したのですが、換金率は83%でした。決して高額の現金化とは言えないと思うのですが、これだけの換金率だったの初めてだったので感動しました。男性スタッフに対応してもらい、正直、最初は「ハズレだ」と、思ったのですが、物腰が柔らかくて安心して取引ができました
事務手数料や振込手数料をゼロスタイルで負担してくれるので、その分多く入金されるので助かりました。たとえ少額の現金化の利用だとしても、ほんの少しでも節約できるならその方が良いので、ゼロスタイルさんは強い味方です。それに、1万円から換金ができるのも良かったです
ゼロスタイルの換金率の高さが気になったので、とりあえず問い合わせてみました。しかし、換金率は83%でした。振込までの時間も5分なんて嘘で、30分以上かかりました。スタッフからは「ホームページに記載されている換金率は最大値で、振込までの時間も最短時間を記載しています」と言われましたが、紛らわしいと思いました
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
19位:ユーウォレット
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
平日:9時~18時
土日祝:9時~17時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://you123w.com/ |
ユーウォレットの特徴
ユーウォレットは換金率と安全性を同時に保証できるように開発されたクレジットカード現金化サービスです。
10万円以上の利用なら90%以上の換金率を保証し、さらに30万円以上の換金なら94%保証で次回には1%の換金率アップが適用されます。
お得に利用できるだけでなく、クレジットカード会社との提携によって安全性を確保しているのもユーウォレットの特徴です。
また、ユーウォレットでは個人向けのパーソナルプランだけでなく、法人向けのビジネスプランも用意しています。ビジネスプランでは換金率が1%上乗せされているのでさらにお得です。
ユーウォレットは1,000万円以上の現金化にも対応していて、複数カードの併用もできるので資金調達に向いています。
ユーウォレットの口コミ
ユーウォレットは確かな安心感がありました。換金率が明言されている通りで、余計な手数料を追加請求されることはありませんでした。必要な金額に合わせてクレジットカードを現金化できるのですばらしいです。
ユーウォレットは安全性が高いと聞いて利用しました。もうユーウォレットで利用した分をクレジットカード会社に払いました。特にこれまで何もトラブルはなかったので、ユーウォレットは安全に取引できる業者だと思います。
スマホ一つで簡単に現金化できるのは良かったです。初めてだったので何か難しい手続きがあるのか不安でしたが、ユーウォレットに電話したらスムーズにできました。わからないことも答えてもらえてとても安心できました。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
20位:パーフェクトギフト
| 最大換金率 |
98.7% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9:00~20:00(年中無休) |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://perfect-gift.info/ |
パーフェクトギフトの特徴
クレジットカード現金化のパーフェクトギフトは、なんといってもそのスピーディーさにあります。
パーフェクトギフトは、現金が今すぐ必要という方のために、一分一秒でも早い入金をモットーにしています。
本人確認や説明などがある初回でも30分から1時間程度、2回目以降は最短5分で入金がされるので急に現金が必要となったときも安心です。
2006年の創業以来カード事故も0で、親切なオペレーターが丁寧に案内してくれるので現金化を初めて利用するという方でもスムーズに利用できるでしょう。
換金率も業界最高水準の98.7%なので、クレジットカード現金化をするならパーフェクトギフトがおすすめです。
パーフェクトギフトの口コミ
現金化は初めてでしたが、オペレーターの方が丁寧に説明してくれたので特に問題なく利用することができました。
時間は初回だったので説明などもあり一時間くらいかかったけれど、二度目からはもっと早くできるみたいです。
換金率98.7%といっていたけれど、手数料がかかるので実際に手元に残るのはもう少し少ないです。
ただ、何回か利用しているけれど2回目からは本当に5分くらいで振り込まれるから便利かな。
とくにトラブルもないし、受付してくれる女の人も親切だからこれからも利用するつもりです。
仕事が忙しくて平日は電話する時間がないので、土日祝日もやっているのがありがたかったです。
借金とかと違って信用情報にのらないから、バレないのがよいと思いました。思ったより手数料はかかったけれど、急ぎのときにもすぐ入金してくれるから満足しています。
21位:88キャッシュ
| 最大換金率 |
98.9% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://www.8cash.biz/ |
88キャッシュの特徴
88キャッシュは高換金率が魅力の現金化業者です。最低換金率が88%で設定されているので、申込後に換金率の低さでがっかりすることはありません。
また、他社からの乗り換えなら平均90%~98%で現金化できるうえ、8のつく日に換金率がアップするキャンペーンなど、とことん高換金率にこだわった現金化業者となっています。
土日祝日も年中無休で営業。即日入金も可能です。創業以来カードトラブルゼロ、個人情報の徹底管理など安全面にも配慮されているため。初めてクレジットカードを現金化する方にもおすすめの業者です。
88キャッシュの口コミ
他業者から乗換ました。まず、換金率が保証されているのがいいですね。実際申込後に蓋を開けてみたら「換金率が低い・・・」なんてことも多いので88キャッシュなら安心です。
8のつく日キャンペーンがリピーター思いだなと感じます。高額利用のみの適用ではなく、3万円以上からキャンペーンンを受けられるのでほとんどの人が適用になると思います。88キャッシュで現金化するなら8のつく日がおすすめです。
初めてだったので、電話で申込をしました。スタッフの対応もよく、キャンペーンの案内など丁寧にやってくれたので、おかげでお得に現金化することができました。振込手数料もかかりませんでした。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
22位:アースサポート
| 最大換金率 |
98.9% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9時~20時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://earthgekinka.com/ |
アースサポートの特徴
アースサポートは、6万人以上の利用実績がある人気の現金化業者です。来店不要で、ウェブサイトからの申し込みですぐに利用できます。
アースサポートの特徴となっているのが、すべてのブランドのクレジットカードに対応していることです。どのカードを利用している方でも、アースサポートで現金化することができます。
また、アースサポートでは個人情報の管理に力を入れているのも特徴です。申し込みの際に送信する個人情報などはきちんと保護されているため、現金化を利用したことが誰かに知られる心配がありません。
そして、アースサポートでは24時間365日の体制で即日振込に対応していることも特徴となります。申し込み手続きから振込までが30分以内と短く、すぐに現金を受け取ることが可能です。土日・祝日の申し込みにも対応しているため、現金が必要なときにいつでも利用できます。
アースサポートでは換金率が91~98.8%と高く、換金率アップのキャンペーンもあるため、お得な現金化をしたい方にも向いています。
アースサポートの口コミ
クレジットカードの現金化に不安がありましたが、アースサポートは申し込みがとても簡単で、スタッフの対応も親切だったので安心できました。現金化について知りたいことがあれば相談に乗ってくれるので、初めての方が利用するのにおすすめです。
アースサポートを何度か利用しましたが、入金スピードが速いのが良いと思います。簡単な申し込みをするだけで、30分程度で振込をしてもらえます。すぐに現金が必要な方は、アースサポートを利用してみてください。
休日に急に現金が必要になったため、アースサポートを利用しました。祝日だったので心配でしたが、その日のうちに入金してもらえました。アースサポートは24時間365日営業しているため、いつでも使えるのが良いと思います。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
23位:スマイルギフト
| 最大換金率 |
99.2% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
記載なし |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://smilegift.org/ |
スマイルギフトの特徴
直近で現金が必要な時に気軽に利用できるサービス。換金率が90%超えなのが魅力的です。
外食やショッピング、自分の時間をもっと有意義に使えます。お金を借りるのに抵抗がある人でも利用しやすいと思います。
他にも他社の金融機関で審査が通らなかった人にもオススメです。安全に利用できるサービスです。年中無休で迅速な対応をしてくれます。
女性オペレーターも多く、要望があれば他のオペレーターが対応してくれます。
メールでの申し込みも可能で、24時間受付をしているのでどんな人でも相談しやすいと思います。
スマイルギフトは、クレジットカードのショッピング枠を現金化する斬新かつ安全なサービスです。他会社を登録したり、他社借入をする事無く自分の持っているクレジットカードで使えるので安心して利用できます。
さらに、スマイルギフトでのクレジットカードの現金化は信用情報機関には登録されません。お支払いに関しても、スマイルギフトからの請求はなく、使用しているクレジットカードの会社からの請求になります。
少しでも自身の今の暮らしの負担を減らしたい、充実した生活をしたいという方にオススメしたい素晴らしいサービスです。
スマイルギフトの口コミ
ホームページはキレイで印象が良く、実際に利用してみても印象通りの現金化作業でした。直接お問い合わせをした際にもオペレーターの方が丁寧に説明してくれたので分かりやすかったです。特にトラブルも無く、安心して利用する事ができています。
電話が24時間いつでも繋がるので非常に助かります。自身の思い立ったタイミングでも手続きする事ができて、振込スピードもとても早かったので忙しい社会人や、時間が無く今すぐお金が必要な人にも助かるサービスだと思いました。
現金化に対して少し怖い印象があったのですが、知人の方から「スマイルギフトの対応が良い」と聞き、初めてこちらを利用しました。現金化について殆ど知らなかったのですが、嫌な態度を取ることなく親切に詳しく教えてくれました。分かりやすい説明のおかげで安心して現金化する事ができました。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
24位:生活ギフト
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
8時~22時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://s-gift.jp/ |
生活ギフトの特徴
生活ギフトは創業16年の実績があるクレジットカード現金化サイトです。還元率89%~98%と業界でもかなり高い水準となっています。
会員特典や大還元キャンペーンなども魅力。
日本全国オンラインでお手続きできますし2018年からは15時以降土日祝日も当日入金が可能です!
ちなみに、振込先は大手銀行はもちろん、地方銀行などほぼすべての銀行に対応しているので新しい銀行口座を作るなどの作業も一切不要です。
そして電話でのサポートも行っているので、安心感がありますよね。オンラインが少し苦手・・という方でも安心してご利用いただくことができます。
現金のクレジット方法に関してはクレジットカードでで提携品の商品を購入していただき購入金額の最大約97.5%の現金を還元するサービスです。
最近ではAmazonギフト券、aupayなどのプリペイドカードなどもお取り扱いをしているので、幅広く現金にすることができます。
生活ギフトの口コミ
今月は美容代、飲み会などで出費がとてもかさんでしまって、たまたま見た雑誌で生活ギフトさんを見つけて申し込んでみました。はじめてだったので1万円だけ試しにやってみたら、すぐに現金が振り込まれてびっくり!とっても助かりました!
学生だと断られることが多くて困っていました、。でも生活ギフトさんに電話で相談してみたらかなり親身になって聞いてくれてAmazonギフト券を買い取ってくれてとてもうれしかったです!これからも利用していこうとおもいます。
口コミで生活ギフトさんを知りました!16年の実績があるということでとても安心して利用することができました。前に同じようなところで還元率50%ぐらいになってしまって痛い目を見ていたのでちょっと不安はあったのですが、手数料10%ぐらいしかとられなくてちゃんとしたところだと思いました!
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
25位:サポートギフト
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
8時~22時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://sp-gift.net/ |
サポートギフトの特徴
サポートギフトは24時間営業で土日祝日も営業しており、最短5分で振り込まれる速さがあります。
最大換金率は高還元率プランの98%です。一部の銀行を除けば、土日祝日や15時を過ぎての即日入金も可能です。
また、手数料が一切かからないと明記されていることは大きな特徴です。
商品を購入しなければ入金されないシステムであり、その対象は情報テキスト類に限定されています。これは小包で届けられますが、伝票などに社名や金額は表示されません。
2種類のプランが有り、即日現金化プランは手続きが完了次第、最短5分で振り込まれます。利用額で換金率は変化し、30万円までは89%、101万円から300万円では96%となります。
高還元率プランは即日プランより換金率が高く、30万円までは91%、101万円から300万円では98%となります。ただし換金率が高い代わりに入金までの日数が長くなりますので、都合に合わせてプランを選びましょう。
営業時間は8~22時で、年中無休です。メールでの申込み、問い合わせは24時間受け付けています。
サポートギフトの口コミ
ネットで換金率が低いという口コミも見かけて不安だった。しかし換金表の通りに現金化してくれない業者が多い中、サポートギフトは換金表通りに現金化してくれた。このため換金率は良いと言えるし、接客態度も良かった。
多重債務を返済したくて、借り入れをサポートギフトを使って一本化した。熱心に相談に乗ってもらえたし、スタッフの対応は丁寧で、好印象だった。サポートギフトさんがいなかったら、まだ返済の目処がつかずに苦しんでいたと思う。
レビューを見て高還元率なら、と利用したが、それだと即日入金ではなかった。また、オフィシャルサイトの説明がごちゃごちゃとしていて読みづらいと感じた。もっと早くやっておけばよかっただけだけど、もっとわかりやすいやり方があればいいのにとも思う。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
26位:ライフパートナー
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短5分 |
| 営業時間 |
9:00~20:00 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://0120447888.net/ |
ライフパートナーの特徴
全国で対応してもらうことができる業者であり、換金最大率としては業界最大級とも言える98%が上限となっています。即日入金も可能であり、顧客満足度も非常に高い業者となります。
簡単、即日、安心、という三つの魅力的なワードが企業ポリシーとなっています。
他社が1%でも高い換金率を提示したと言うのであれば、それに即対応してくれると言うことになっています。実際のところの換金率は86%から98%となっていてその中から決められるという形になるわけです。
三つのプランが用意されていて、即日プラン、レディースプラン、バリュープランというのがあります。対応しているクレジットカードも日本国内で発行されたものは全て対応可能ということでその点も優秀な業者となっているのです。
15時を過ぎても20時までに振込ことが可能であり、ほぼすべての都市銀行、地銀などに対応してもらうことができる、かなり柔軟性の高い、応用力があるクレジットカード現金化業者になります。
ライフパートナーの口コミ
どうしてもお金が必要になってしまったので現金を手に入れるために重要させていただきました。
細かい説明とかもしっかりとしてもらうことができましたし、 ちょっと不安になっている部分ないともう一つ一つその不安理由を取り除いてくれるような話をしてもらうことができました。
女性でも安心できるサービス内容でした。女性プランがあるというのは非常に助かりました。換金率なんかに関しては高いか低いのかはよくわからない部分もありましたが、少なくとも満足できるものではありましたからよかったです。
ちょっとした事情でお金が借りられないのでこういうサービスで現金を急な時に用意できるのは有難いことでした。対応も丁寧であり、不安もありましたが特にトラブル何かがその後に起きるということもありませんでしたし、また利用したいところです。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短5分でお振込み
27位:なごみギフト
| 最大換金率 |
98.9% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
24時間 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://nagomigift.com/ |
なごみギフトの特徴
なごみギフトの特徴は複数のプラン、実績の長さ、国内のほとんどのカードに対応といった点が挙げられます。
まず、複数のプランが用意されています。
なごみギフトで用意されている、当日に入金される当日プラン、通常プラン、そしてキャンペーンプランの3つです。
当日プランは、当日入金を確実に行、急いでいる方におすすめなプランといえるでしょう。
通常プランは、換金率が上がるプランで急いでいない方におすすめのプランといえます。
最後のキャンペーンプランは新規利用の方限定のプランです。
換金率が高く、当日入金並みのスピードで換金してくれるプランです。
実績も長く、13年以上の実績を持ちます。いい加減な業者であれば、そこまで事業が継続できません。
それだけなごみギフトは信頼できる業者といえるでしょう。
国内のほとんどのカードにも対応しています。
VISAやMasterCardといったブランドはもちろん、他の業者が断るようなJCBやAmericanExpress、そしてダイナースクラブにも対応しています。
ブランドを気にすることなく利用できるのはメリットといえるでしょう。このような魅力がなごみギフトの特徴です。
なごみギフトの口コミ
ナビゲートしてくれた方が親切で、振込も思った以上に早かったですね。初めてのクレジットカード現金化でしたが、電話口で丁寧にガイドしてくれました。カードトラブルが心配だったので質問したら、安全性についてもしっかり説明してくれたのは好印象。
きちんと当日振り込みをしてくれました。当日プランで申し込んだので当然なのですが、他の業者はそうじゃないこともあるみたいな情報を知っていたので、安心でした。忙しくてこちらは焦っていましたが、電話対応してくれた方が丁寧に落ち着いて対応してくれたのでその点も助かりました。
手数料の存在を忘れていてホームページの換金率よりも少し少なめの入金でした。ただ、手数料は比較的安くて納得の金額だったので大幅な目減りがなくてよかったと思います。換金率で利用しても安定して現金を渡してくれる業者だと思います。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
28位:かんたんキャッシュ
| 最大換金率 |
98% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
9時~21時 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://kantan-c.com/ |
かんたんキャッシュの特徴
かんたんキャッシュは日本一簡単でクレジットカード現金化をモットーに運営しています。
その為、急な出費が必要となった時は間違いなく強い味方になってくれます。利用者は7万人を超えておりリピート率も83%と利用者の満足が非常に高い現金化業者です。
業界トップクラスの還元率も魅力的で1万円から30万円の少額利用でも91%の還元率で利用する事が出来ます。
来店不要で専用フォームから申し込めば最短3分で現金を手にする事が出来ます。
365日全国どこからでも利用できるのでもしもの時に非常に便利です。初めて利用する人は個人情報の扱いも気になるはずです。
ホームページ上にプライバシーポリシーをしっかり掲げている会社ですから全く心配は要りません。カード事故歴はありませんし顧問弁護士指導の下に運営しているので安心して利用できます。
創業は18年を超えており信頼の実績を持っています。女性スタッフが常駐しており判らない事にもしっかり応えてくれるので不安が残りません。
このようにお客様第一主義が特徴の現金化業者です。
かんたんキャッシュの口コミ
スマホから申し込んだのですが全く迷うことはありませんでした。審査も無く本当にすぐ現金を手にする事が出来て助かりました。還元率も他社より高くスピード性もあるので満足です。込んでいる時でも10分ほどで入金されるのは驚きです。
家族や会社にバレないか不安でした。しかし、勧誘のはがきが届く事も無いですし会社への在籍確認もありません。こっそり利用する事が出来て本当に助かりました。ちゃんと個人情報の保護には力をいてれいるようで安心して利用しています。
不明な点があったので電話で質問したら判り易く丁寧な回答が貰えました。お陰で納得して申し込みをする事が出来ました。電話する時は緊張しましたが優しいオペレーターの対応にほっとしました。手際よく説明してくれたので理解するまで時間も掛からず助かりました。
詳細を見る無料お見積りはこちら
最短3分でお振込み
29位:OKクレジット
| 最大換金率 |
99.7% |
| 入金スピード |
最短3分 |
| 営業時間 |
24時間受付 |
| おすすめ度 |
|
| 公式URL |
https://ok-credit.net/ |
OKクレジットの特徴
OKクレジットは、2012年創業のクレジットカード現金化業者で5年連続顧客満足度NO1を取得しています。振込時間は最短3分となっており、
最大換金率は99.7%、2回目以降は換金率が3%アップするサービスを提供しています。
個人情報も弁護士指導の下、管理を徹底しており、カード事故のリスクも心配不要。不正利用の心配もいりません。
利用にあたって審査や在籍確認も必要なく、スムーズにクレジットカードを現金化できます。
OKクレジットの口コミ
オペレーターの対応もよく、初めて利用する私も安心して現金化できました。不安だった振込スピードも満足でしたので、次もOKクレジットを利用しようと思います。
流石に最大換金率の99.7%は適用されませんでしたが、思ったよりも換金率が高かったので、見積後すぐに申込ました。その日のうちに現金が振り込まれたので、遅延することなく支払いすることができました。
週末に利用しましたが、24時間対応の金融機関だったのですぐに入金を確認できました。OKクレジットの対応の速さに驚きです。急いでいる人にはおすすめです。
クレジットカード現金化優良店比較|100業者以上を徹底調査

 メディア編集部
メディア編集部
クレジットカード現金化をしようにも多くの現金化業者があるため、どの現金化業者を利用すれば良いのか迷ってしまうはず。
こちらでは、様々な項目で比較して優良現金化業者をご紹介します。

換金率で比較
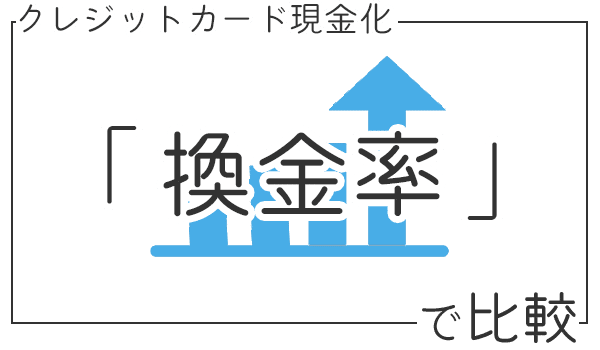
クレジットカード現金化を利用する上で利用者が最も気にすることが換金率。
それでは、換金率の高い現金化業者を比較していきましょう。
換金率の概要や比較する際のポイント
現金化の換金率で気をつけなければならないことは、一般的に公式サイトに記載されている換金率と実際の換金率は異なること。
よく公式サイトには「最大換金率98%以上!」とありますが、購入金額の98%以上の現金が手に入ることはありません。
実際の換金率は平均75%前後で、80%以上になると高換金率の現金化業者と呼ばれます。
 メディア編集部
メディア編集部
それでは、高換金率を提供するおすすめトップ3の現金化業者を紹介しましょう!
換金率が高い業者ベスト3
換金率が高いおすすめの現金化業者は以下のとおりです。
換金率が高い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
換金率 |
公式 |
 |
 いますぐクレジット いますぐクレジット |
99.5% |
詳細 |
 |
 スピードペイ スピードペイ |
98% |
詳細 |
 |
 ゼロスタイル ゼロスタイル |
99.2% |
詳細 |
まずは、いますぐクレジットの換金率ですが、なんと99.5%!かなりの換金率といっていいでしょう。
もちろん利用料金によります。しかし、1万円の利用でも換金率は約91%と超良好です。
また、スピードペイも98%と換金率が高く、ゼロスタイルに関しても最大99.2%と他社を抜きに出ています。
振込スピードで比較

クレジットカード現金化を利用する際にチェックしたいポイントのひとつが振込までのスピードです。
では、一体どんな現金化業者がスピーディーに対応してくれるのでしょうか。
振込スピードの概要や比較する際のポイント
まず、考えてみてください。
あなたがクレジットカード現金化を利用するときはどんなときですか。
誰もが現金が今すぐにでも欲しいときと答えるはず。
そのため、現金化業者を利用するときには申し込みから振込までのスピードが大切なのです。
しかし、一般的に初回利用者は本人確認があるためリピーターよりも時間がかかります。
 メディア編集部
メディア編集部
平均すると30~60分とされていますが、優良業者の条件は30分前後であることです。それをふまえた上で、振込スピードが早い業者はこちらです。
振込スピードが早い業者ベスト3
振込スピードが早い現金化業者はこちらになっています!
振込スピードが早い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
振込スピード |
公式 |
 |
 現金化ベスト 現金化ベスト |
3分 |
詳細 |
 |
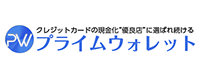 プライムウォレット プライムウォレット |
15分 |
詳細 |
 |
 スピードペイ スピードペイ |
15分 |
詳細 |
24キャッシュはなんと約10分で、プライムウォレットとスピードペイは15分で振込可能ということで、スピードではピカイチがそろっています。
24キャッシュに関しては平均以上の速さです。
ただし、スピードは日時や込み具合によって異なるので覚えておいてくださいね。
接客対応で比較
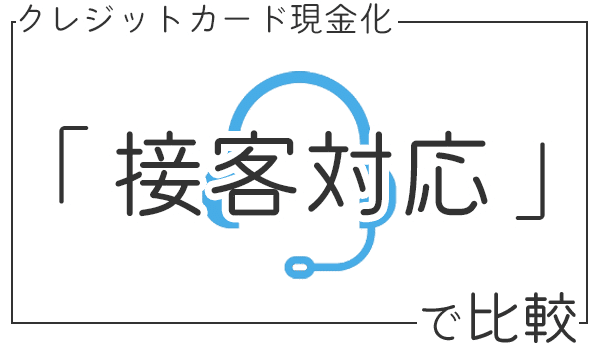
初めて現金化を利用する人にとって気になるのが業者の接客対応です。
いまだに現金化=消費者金融といったイメージは、残念ながらぬぐえていません。
そのため、現金化業者のスタッフの対応は怖いという先入観を持った人も多いので、接客態度の良さで業者を比較してみました。
接客対応の概要や比較する際のポイント
接客対応の良さは次のようなことを満たすスタッフがそろっている業者です。
- スピーディーに対応してくれる
- 細かい質問にも答えてくれる
- 無料サービスが豊富
先にも伝えたように、現金化を利用する人はお金が欲しくて急いでいます。
それなのにもたもたされたら困りますし、質問にスムーズに応えられない業者は信頼がおけませんよね。
さらに、見積もりや相談といったサービスが無料でできる現金化業者は意外と少ないので、公式サイトに「見積もり無料」と掲げている業者は比較的信用できる業者といえます。
 メディア編集部
メディア編集部
それでは、接客対応が良い業者を3つピックアップして見たので要チェックですよ!
接客対応が良い業者ベスト3
接客対応が良いと評判の現金化業者は次の3店舗となります。
接客対応が良い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
接客満足度 |
公式 |
 |
 GENKINKA ITORI GENKINKA ITORI |
|
詳細 |
 |
 タイムリー タイムリー |
|
詳細 |
 |
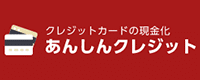 あんしんクレジット あんしんクレジット |
|
詳細 |
まず、タイムリーは、言葉遣いはもちろん、キャンペーンの紹介など、無駄のない接客が好評です。
GENKINKA ITORIは女性社員が多くて安心度を求めるユーザーからの満足度が高いです。
もちろん、女性スタッフなので接客対応も細かい配慮がきいています。
そして、あんしんクレジットは換金率もスピード、安全性も抜群で、接客対応も満足度が高く、おすすめの現金化業者です。
情報公開度で比較

今の時代は個人情報を流すことはNGですが、企業の情報を公開していくことは求められている要素。
現金化業者も情報公開をすることでより信頼度が増しますよね。
情報公開度の概要や比較する際のポイント
クレジットカード現金化業者の情報公開度は、一般企業と比較すれば極めて低いです。
理由としては、やはり現金化がグレーな行為であること、また、単純に公式サイトの内容が不十分であることが挙げられます。
しかし、できるだけ現金化業者の中でもクリアな存在であることをアピールしようと、比較的詳細な会社概要やできる限り細かい情報を与える公式サイトを作る業者も出てきました。
やはり、ポイントとしては会社概要の濃さが重要。
 メディア編集部
メディア編集部
現金化業者のほとんどが代表者名や所在地を明記していません。そのため、会社概要やそれ以外の情報が細かいほど情報公開度の高いといえます。
情報公開度が明瞭な業者ベスト3
情報公開度の高い業者を3つピックアップしてみました。
情報公開度の高い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
情報公開度 |
公式 |
 |
 現金化ベスト 現金化ベスト |
|
詳細 |
 |
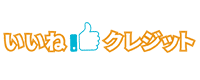 いいねクレジット いいねクレジット |
|
詳細 |
 |
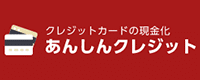 あんしんクレジット あんしんクレジット |
|
詳細 |
現金化BESTも基本的な利用の流れからサービスの内容、気になる換金率や企業内容も比較的詳細です。
そして、あんしんクレジットも利用しやすい金融機関情報やどんなクレジットカードが利用できるのかも一目瞭然。
情報公開されている現金化業者は安心して利用できることにもつながります。
営業時間で比較
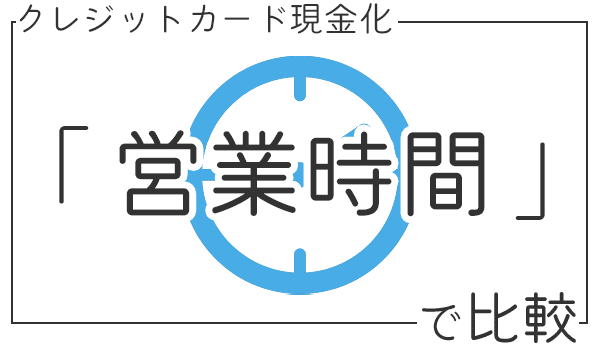
現金化が必要になるときは土日祝日、さらに平日であっても深夜にやっていないと、いざというときに役に立ちませんよね。
だからこそ営業時間は現金化業者を選ぶ上で重要です。
営業時間の概要や比較する際のポイント(土日祝日の営業含む)
クレジットカード現金化業者は、基本的に365日やっている業者がほとんど。
そのため、基本的に365日営業している現金化業者は当たり前です。
重要になってくるのが毎日の営業時間の長さです。
優良業者といわれている業者はいくつかありますが、まるで一般企業かのように平日は9:00~18:00といった営業時間もあれば、土日になるとさらに営業時間が短くなることもあります。
 メディア編集部
メディア編集部
24時間営業している業者は数えるほどしかないので、できるだけ長時間営業の業者を見つけないと利用には不便となるのです。
営業時間がおすすめな業者ベスト3
営業時間的におすすめできる現金化業者が次の3店舗です。
長時間営業の現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
時間営業 |
公式 |
 |
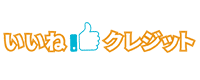 いいねクレジット いいねクレジット |
24時間営業 |
詳細 |
 |
 GENKINKA ITORI GENKINKA ITORI |
24時間申込可能 |
詳細 |
 |
 タイムリー タイムリー |
8:00~20:00 |
詳細 |
残念ながらいずれも24時間営業ではありませんが、紹介した2店舗はいずれも24時間申込が可能なので、他社よりも利用しやすいといえます。
営業時間が長ければ利用のしやすさも抜群。
つまり、利便性の高い現金化業者だといえます。
安全性で比較
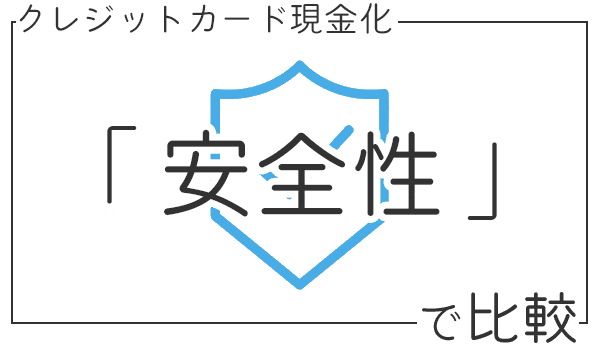
クレジットカード現金化をするときに利用者は換金率を重視しがちですが、最も重要なことは安全性です。
なぜ安全性が重要なのか、また、安全性の高い現金化業者を紹介していきます。
安全性の概要や比較する際のポイント
まずは、安全性の高い現金化業者とは一体どんな業者なのかをまとめてみたので見てみましょう。
- カードトラブルゼロ
- カード明細に詳細が載らない
- 法律のプロが携わっている
クレジットカード現金化はカード規約に違反する行為です。
そのため、カード会社に現金化していることがバレるとカード利用停止になり、最悪の場合、カードがはく奪されることもあります。
また、セキュリティ対策の弱い現金化業者を使うことでカード情報やその他の個人情報が漏洩することもあるため、カード事故が今までにない現金化業者を選ぶことはマスト。
さらに、現金化業者を利用したことがバレるのはカード明細からがほとんどなので、カード明細にも工夫がされていることが大切です。
そして、現金化はハッキリってグレーな行為なので、できる限り法に触れないようにしなければなりません。
そこで、最近増えているのが法律のプロが監修する現金化業者です。
 メディア編集部
メディア編集部
法律のプロがバックにいるので、カードトラブルも避けられ、よく聞かれる換金率の悪さでのトラブルといったことも避けられます。
安全性がしっかりしている業者ベスト3
安全性が高いと評判の現金化業者TOP3は次の3店舗です。
安全性が高い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
安全性 |
公式 |
 |
 どんなときも。クレジット どんなときも。クレジット |
法務部門有り |
詳細 |
 |
 かんたんキャッシュ かんたんキャッシュ |
顧問弁護士指導 |
詳細 |
 |
 88キャッシュ 88キャッシュ |
法律専門家に確認 |
詳細 |
いずれも法律のプロが監修する・携わる現金化業者なのでトラブルが起こりにくいメリットがあります。
初めてクレジットカード現金化をするかたにとっては現金化の安全性は非常に不安なところ。
しかし、こういった安全性の高い現金化業者を選べば安心して利用することができますよね。
盗難紛失対策で比較
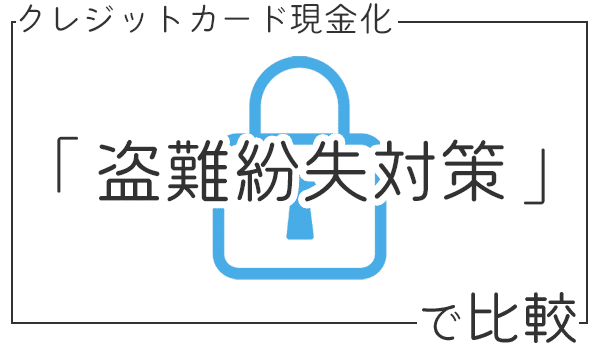
無店舗型の現金化業者でクレジットカード現金化をする際にはカードを提出するわけではないのでカード自体の盗難や紛失はありません。
しかし、悪徳業者を使ってしまうと個人情報が漏洩したりすることはあります。
盗難紛失対策の概要や比較する際のポイント
先述したように、無店舗型(インターネットのみで運営する)現金化業者にカード本体を渡すわけではないので物理的な紛失や盗難はありません。
しかし、個人情報が漏れてしまうことはあります。
そんなときにスマートに対応してくれるのがこんな現金化業者です。
- 長時間営業していること
- サービスが充実していること
- 老舗であること
何か問題が起きた際に営業時間の短い現金化業者では営業時間外で連絡できない可能性があるので、できるだけ営業時間が長いことは重要です。
そのため、サービスが充実している業者もマスト。
さらに、老舗の業者は利用者のトラブルにも対処した経験や実績があるはずなので、老舗業者を選ぶこともポイントです。
 メディア編集部
メディア編集部
接客対応がよく、(無料の)サービスが充実している業者でないと、トラブルに対処してくれない可能性があります。
盗難紛失対策がしっかりしている業者ベスト3
では、盗難紛失対策に強い現金化業者を紹介しましょう。
盗難紛失対策がしっかりしている現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
盗難紛失対策 |
公式 |
 |
 どんなときも。クレジット どんなときも。クレジット |
|
詳細 |
 |
 ゼロスタイル ゼロスタイル |
|
詳細 |
 |
 インパクト インパクト |
|
詳細 |
顧客満足度が高い上記3店舗は、営業時間も長め。
また、接客対応やサービスに関しても顧客満足度の高さから良いことは言わずもがなですよね。
そもそも、カードトラブルといったアクシデントを起こしたことのない業者ですが、利用者のアクシデントにしっかりと対応してくれる心強い業者と言えます。
運営年数で比較
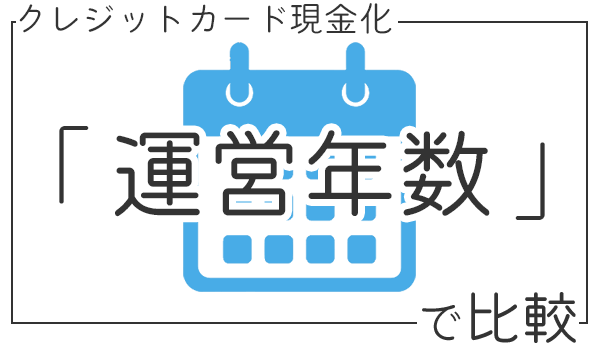
クレジットカード現金化はここ最近よく聞かれるようになった言葉かもしれませんが、じつは結構前からあります。
しかし、昔から続いている現金化業者はごくわずか。
そこで、運営年数の長い現金化業者をピックアップしてみました。
運営年数の概要や比較する際のポイント
現金化業者の運営年数も必ずチェックしたいポイント。
新しい現金化業者は実績がなく、口コミ数も少ないのであまり信用がおけません。
運営年数が長ければ実績や経験が豊富ですし、そもそも現金化業者で10年前後続く業者は稀なケース。
長年運営してきている=トラブルがなく、安心して利用できる業者だと判断できます。
各業者の運営で気は会社概要や公式サイトのトップに「創業◯◯年」と掲げる業者もあるのでチェックしてみましょう。
 メディア編集部
メディア編集部
ただし、創業年数を偽っている業者もあるので注意が必要です。
運営年数が長い業者ベスト3
運営年数の長い現金化業者を3つピックアップしてみたのでご覧ください。
運営年数が長い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
運営年数 |
公式 |
 |
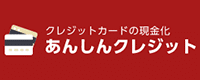 あんしんクレジット あんしんクレジット |
22年 |
詳細 |
 |
 セーフティーサポート セーフティーサポート |
20年 |
詳細 |
上記3店舗はいずれも約15年もの運営歴をもつ現金化業者なので、現金化においては老舗業者と呼べます。
老舗を利用すれば現金化についてももちろん詳しく理解しているので信頼がおけます。
大手現金化優良店か?で比較
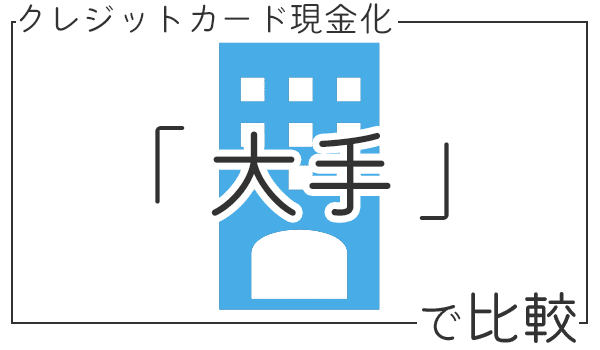
現金化業者を利用する際にはできるだけ大手の業者を使うのがおすすめ。
やはり、実績と経験豊富の業者に頼んだ方が精神的にも安心できますし、現金化に慣れているため安全でもあります。
なぜ大手が良いのかの概要や比較する際のポイント
大手の現金化業者を利用するのがおすすめなことは前述したとおり。
大手現金化業者と呼ばれる業者の主な特徴は以下のようになっています。
- 長年運営している
- 優良業者である
- ほどよい露出である
当然、大手現金化業者は老舗、つまり長年運営していることが条件となります。
できたばかりの業者では大手とはもちろん言えませんし、信頼もおけませんよね。
そして、優良業者であること。
必然的に優良業者はリピーターがつきやすいので長期運営につながるだけでなく、高換金率で接客対応も良いことがほとんどなので、これから益々大きな業者となることが予想されます。
最後にほどよい露出度であることも大切。
 メディア編集部
メディア編集部
誇大広告をする業者が現金化業者には多いですが、誇張しすぎない「真実に近い」情報を与える業者は大手と呼べます。
大手現金化業者ベスト3
それでは、おすすめの大手業者と呼べる現金化業者ベスト3を発表していきましょう。
大手現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
優良店度 |
公式 |
 |
 ブリッジ ブリッジ |
|
詳細 |
 |
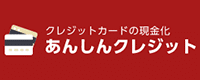 あんしんクレジット あんしんクレジット |
|
詳細 |
 |
 GENKINKA ITORI GENKINKA ITORI |
|
詳細 |
いずれの業者も10年以上の実績を持つ現金化業者なので、現金化では老舗と言えます。
さらに、誇大広告をしている業者もありますが、他社よりも表記と実際の換金率に違いはありませんし、当然ながら優良業者と口コミや他の比較サイトからも判断できる業者となっているので安心・安全に利用できる大手現金化業者です。
キャンペーンで比較
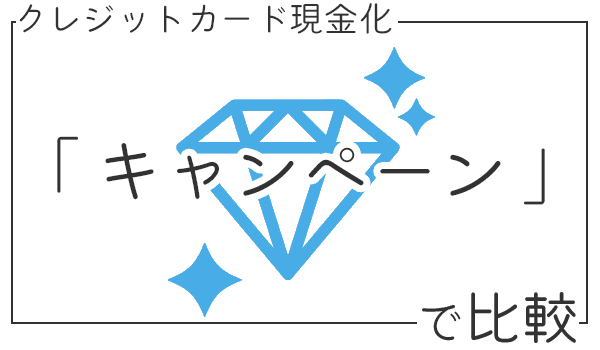
ほとんどの現金化業者においてキャンペーンを設けています。
キャンペーンを使うことでお得にクレジットカード現金化ができる、そんな現金化業者について紹介していきましょう。
キャンペーンの概要や比較する際のポイント
キャンペーンを提供する現金化業者は少なくないことは伝えたとおりです。
しかし、キャンペーンにつられて現金化業者を選ぶのは絶対にNG。
キャンペーンで現金化業者を選ぶ際には次のようなポイントに気をつけましょう。
- いくらの利用額から利用できるのか
- キャンペーンの無い他社の換金率と比較する
じつは、業者が行うキャンペーンには裏があり、基本的には高額現金化をする人が対象となります。
そのため、いくらの利用額から利用できるキャンペーンかを明確にすることがマスト。
そして、もともと換金率の低い現金化業者であればキャンペーンを行っていない業者よりもキャンペーンを使ったのに換金率が低い場合もよくあることです。
 メディア編集部
メディア編集部
高換金率を狙うのであれば、キャンペーンの内容につられるのではなく、キャンペーンを使わなくても高換金率となる現金化業者を選ぶ方がスマートです。
キャンペーンがすごい業者ベスト3
キャンペーンの内容が充実している現金化業者は次の3つの業者です。
キャンペーンがすごい現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
キャンペーン |
公式 |
 |
 ブリッジ ブリッジ |
|
詳細 |
 |
 タイムリー タイムリー |
新規1.5~5万円プレゼント |
詳細 |
 |
 インパクト インパクト |
新規利用で換金率が2%UP |
詳細 |
ブリッジは「男性プラン」などのキャンペーンが豊富です。
タイムリーは新規利用者限定で1.5~5万円の現金がプレゼントされます。
さらに、インパクトは新規利用者は換金率が2%アップするなど、ビッグなキャンペーンが行われているので注目です。
ただし、キャンペーンの適用条件が具体的に示されていたとしても、必ず利用前に業者に確認しましょう。
確認せずにキャンペーンが適用されると思って利用するとキャンペーンがつかないといったケースは少なくありません。トラブルは未然に防ぐようにしましょう。
口コミで比較
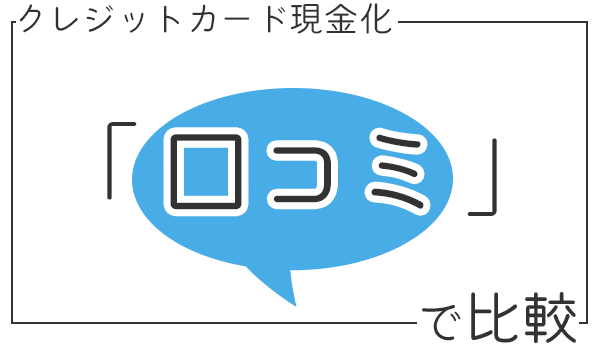
口コミは利用者のリアルな声。
ということで、やはり業者の良し悪しを知る上で絶対にチェックしたいポイントですよね。
口コミの概要や比較する際のポイント
クレジットカード現金化をする前に、気になっている業者はもちろん、そうでない業者も利用前に口コミをチェックするのはマストです。
ただし、現金化に限らず、口コミをすべて鵜呑みにするのはやめてください。
あくまでも口コミは個人の意見であり、現金化に関して言えば、混雑状況や曜日によっては状況が異なります。
口コミは参考程度にとどめることがおすすめ。
では、具体的に口コミで現金化業者を選ぶならどんなポイントをチェックするのかを見ていきましょう!
- 良い口コミだけは信じるな!
- 接客・換金率・スピードがパーフェクト!
- 公式サイトと同換金率で換金した口コミは信じない
良い口コミだけの業者は自作自演である可能性が高いです。
つまり、業者が利用者のように書いた口コミなので信用してはいけません。
一般的に考えて自ら良い口コミを書くことはあっても悪いことは書きませんよね。
あえて悪い口コミがあるのはちゃんと利用者がいることがわかりますし、それ以上に良い口コミがあれば、リアルな口コミだと捉えることができます。
また、公式サイトと実際の換金率が異なることは伝えている通りなので、公式サイトと同じ換金率で換金してもらえたという口コミも信じるべきではありません。
 メディア編集部
メディア編集部
接客・換金率・スピードがパーフェクトである「優良業者」であることが口コミでも良い現金化業者となります。
口コミ評判の良い業者ベスト3
口コミ評判の高い現金化業者をピックアップしてみました。
口コミ評判の高い現金化業者TOP3
| 順位 |
現金化業者 |
口コミ評判 |
公式 |
 |
 いますぐクレジット いますぐクレジット |
|
詳細 |
 |
 スピードペイ スピードペイ |
|
詳細 |
 |
 ブリッジ ブリッジ |
|
詳細 |
上記はいずれも口コミで評価の高い3店舗。
やはり、口コミで評価が高くなるポイントとしては換金率の高さが挙げられます。
いずれも平均80%以上であり、安全性も抜群、情報公開度も高く、まさに優良業者で、口コミで評価が高くなるのは当然のことです。
クレジットカード現金化優良店比較表
スクロールできます
クレジットカード現金化比較表
| 現金化業者 |
換金率 |
最短振込
スピード |
口コミ |
電話対応
接客 |
 タイムリー タイムリー |
93~98.6% |
5分 |
|
|
 ブリッジ ブリッジ |
91~99.5% |
3分 |
|
|
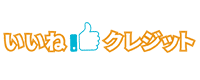 いいねクレジット いいねクレジット |
91~98% |
5分 |
|
|
 GENKINKA ITORI GENKINKA ITORI |
91~99.5% |
15分 |
|
|
 現金化ベスト 現金化ベスト |
99.2% |
3分 |
|
|
 ソニックマネー ソニックマネー |
99.2% |
3分 |
|
|
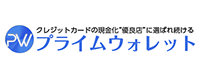 プライムウォレット プライムウォレット |
88~98.3% |
10分 |
|
|
 ラストチェンジ ラストチェンジ |
88~98.40% |
10分 |
|
|
 トラストキャッシュ トラストキャッシュ |
93~99.5% |
15分 |
|
|
 オレンジチケット オレンジチケット |
70%~88% |
5分 |
|
|
 スピードペイ スピードペイ |
94~記載なし |
10分 |
|
|
 ゼロスタイル ゼロスタイル |
88~99.2% |
5分 |
|
|
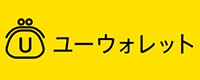 ユーウォレット ユーウォレット |
90~98% |
5分 |
|
|
 パーフェクトギフト パーフェクトギフト |
94~98.7% |
5分 |
|
|
 どんなときも。クレジット どんなときも。クレジット |
88~98% |
10分 |
|
|
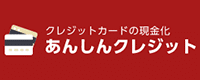 あんしんクレジット あんしんクレジット |
91~98% |
10分 |
|
|
 インパクト インパクト |
93~97.8% |
5分 |
|
|
 スマイルギフト スマイルギフト |
92~99.2% |
3分 |
|
|
 キャッシュライン キャッシュライン |
88~98.8% |
5分 |
|
|
 かんたんキャッシュ かんたんキャッシュ |
91~98% |
3分 |
|
|
 ひまわりギフト ひまわりギフト |
記載なし~96% |
5分 |
|
|
 セーフティーサポート セーフティーサポート |
91~98% |
5分 |
|
|
 88キャッシュ 88キャッシュ |
88~97% |
3分 |
|
|
クレジットカード現金化優良店の選び方

現金化優良店を見つける際に、チェックしていただきたいポイントを覚えておいていただきたいと思います。
 メディア編集部
メディア編集部
優良現金化業者選びのポイントはこんな感じになっています。
 メディア編集部
メディア編集部
それでは、それぞれのポイントについて細かく見ていきましょう
カードトラブルを起こしていないこと
クレジットカード現金化は、決しておすすめできる行為ではなく、グレーな行為だといえます。
違法行為ではありませんが、極めて違法に近い行為と言っても過言ではありません。
簡単に現金を手にすることができる方法かもしれませんが、とてもリスキーな行為で、カード会社に現金化していることがバレてしまうとカード利用停止のリスクはもちろん、カードをはく奪、強制退会になった上に残債を一括返済させられます。
もちろん、その後数年間はブラックリストに記載されるため、新しいクレジットカードをどのカード会社でも作成することはできません。
ですから、創業以来1度もカードトラブルを起こしたことのない現金化業者を選ぶことは絶対条件です。
 メディア編集部
メディア編集部
カードトラブルを起こしたことがない現金化業者はホームページに大々的に表記していますよ。
今やクレジットカードがなければ生活できないなんて方も多いでしょうから、クレジットカードのない生活になりたくなければ安全性の高いトラブル経験のない現金化業者を選ばないと、大きな被害をもたらすことがありますのでご注意ください。
会社概要が明確であること
どんな企業のホームページにも会社概要が掲載されているのは当然のことですが、現金化業者の場合、当たり前のことが当たり前ではないのです。
会社概要をホームページに載せていない現金化業者も少なくありませんし、会社概要があってもほとんどの場合、所在地を濁していたり、代表者名など、一般企業であれば必ず記載されているはずの情報が記載されていません。
 メディア編集部
メディア編集部
ということで、各現金化業者のホームページではこんなことをチェックしましょう。
代表者名は偽名を使っている可能性も考えられますが(優良業者であってもお金を扱う業務なのでトラブルが起こり得るので、危険を回避する策)、記載されていないより記載されていた方が信頼は増すので、この点もチェックしましょう。
また、一番チェックするべき点である所在地は、〇丁目だけや最終的な番地の記載のみであったり、詳細が記されていると思ったらバーチャルオフィスの住所であることがよくあります。
 メディア編集部
メディア編集部
グーグルマップなどを利用して、会社概要にある所在地を細かく調べてみると良いでしょう。
さらに、設立年に関してもホームページに「創業10年!」などと大々的に掲げる現金化業者はよくありますが、実はよく調べてみると設立してから数年しか経っていないことが現金化業者ではよくあるのです。
「嘘」を掲載している現金化業者は、やはり優良業者とは言い難いので、その時点でクレジットカード現金化を申し込むことはやめた方が無難です。
逆に、設立年が書いてある現金化業者はある程度信頼できる業者だと考えて良いでしょう。
換金率が高いこと
クレジットカード現金化を利用する上で利用者が一番気になる点なので、これは問題ないかもしれません。そうです、換金率が高いことです。
 メディア編集部
メディア編集部
そもそも、「換金率が高い」とは、どのくらいのパーセンテージからなのかご存知ですか?
先ほどお伝えしたように、換金率の相場が75%で、優良業者の換金率は80%以上であることが絶対条件ですので押さえておきましょう。
このように、なぜ換金率が高いことが重要だと思いますか?
もちろん、現金化利用者にとって入金されるお金が増えることが大きな理由の1つですが、換金率が高い現金化業者は、消費者のために無駄な手数料を抑えていると言える、つまり優良業者なのです。
優良業者を選べば安全にクレジットカード現金化することができるので、換金率が高い現金化業者を選ぶことは、安全を買うことにもつながります。
 メディア編集部
メディア編集部
実際の換金率は必ず各現金化業者に問い合わせてくださいね
実績や経験(運営年数が長い)が豊富であること
現金化業者を選ぶ時に限らず、どんなことでも実績や経験がない企業に何かを依頼する、ましてやお金が絡む件を頼むのはかなりの賭けとなりますし、失敗につながってしまうこともありますよね。ですから、実績や経験豊富な現金化業者を選んでください。
新しくできたばかりの現金化業者は実態がつかみにくいので、運営年数が長い現金化業者を選ぶことも覚えておきましょう。
「顧客満足度1位」、「リピーター率1位」、「優良店ランキング1位」などと、ホームページに掲げている現金化業者は実績がある証です。
とはいえ、自作自演の実績を掲げるホームページもあるので、実績が本物かどうかをしっかりと見極めてください。
営業時間が長いこと
土日・祝日に営業している現金化業者を選ぶことと同じことですが、できるだけ長く営業している現金化業者を選ぶことも大事です。
現金化業者の営業時間は、それぞれです。平均すると、9:00~20:00を営業時間としている現金化業者が多いのですが、中には一般企業のように9:00~18:00、さらには土日/祝日休みにしている現金化業者もあります。
 メディア編集部
メディア編集部
確かに、そこで働く社員のためには良いですが、利用者としてはデメリットですよね。
逆に、24時間営業の現金化業者も増えてきています。営業時間が長い現金化業者を選べば、いつでも好きな時にクレジットカード現金化をすることができますし、何かあった時にもすぐに連絡して対処してもらえるので利便性が高いのです。
ですから、できる限り営業時間が長いことを選ぶ現金化業者を選ぶことは重要です。
口コミ評判があること
特に、初めてクレジットカード現金化をするのであれば直感で「この業者はよさそう」だと思って利用すると、トラブルとなる可能性も高いです。
現金化業者を選ぶ際には利用者の声をチェックすることが大切となりますので、口コミ評判をいくつか見てみましょう。
ただし、現金化業者の良い口コミに関しては自作自演(業者が自ら自社のコメントをしている)が多いので、どれが実際に利用した人の本当の口コミかをしっかり判断してください。
 メディア編集部
メディア編集部
自作自演の口コミは明らかに良すぎることしか書いていないのですぐにわかりますよ。
口コミをチェックすれば、利用しようと考えている現金化業者が優良かどうかをある程度判断することができますが、100%鵜呑みにせず、「参考」までにとどめてください。
スタッフの対応の良さ
スタッフの対応は、会社を映す鏡といって良いでしょう。まずは、気になる現金化業者はすべてに電話をかけて換金率を確認するなどしてみてください。
 メディア編集部
メディア編集部
その際のスタッフの対応が良ければ安心して利用することができますよね?
現金化業者の口コミを見ていただくとわかるのですが、
スタッフの対応の悪さについて書かれている口コミはたくさんあります。
中には、脅迫じみたことを言われたケースもありますので、スタッフの対応が良い現金化業者を選ぶことも安全にクレジットカード現金化を行う絶対条件です。
振込までスピーディであること
クレジットカード現金化を行う人に共通して言えることが、今すぐお金が欲しいことです。
現金化業者によって、振り込みまでのスピードは異なります。ホームページには「振込まで最短5分」と掲げているにもかかわらず、実際に利用してみたら振り込まれるのに3時間もかかったなんて話はよくあるのです。
通常、オンライン決済が終わってから振込までにかかる時間は、30~60分(初回利用者)であれば優良業者だと言われているので、目安としてください。
ただし、その現金化業者で初めてクレジットカード現金化を行う場合、本人確認作業を行う必要があるためリピーターよりも振込までに時間がかかることかかるのでご注意ください。
クレジットカード現金化比較サイトのメリットと注意点

クレジットカード現金化比較サイトを利用する際の、メリットや注意点についてまとめました。
クレジットカード現金化比較サイトのメリット
それではさっそく、現金化比較サイトのメリットを以下にまとめました。
 メディア編集部
メディア編集部
調べる手間が省ける
おそらく、あなたが調べた現金化業者はきっとたくさんあるでしょう。
しかし、それはほんの一部であってあなたが調べた現金化業者以外にも、全国に数えきれないほどの現金化業者があります。
そんなたくさんある現金化業者を、ひとつひとつチェックしていたら時間も手間もかかってしまいますが、比較サイトを使えば最初から大手や有名な業者をピックアップしているため、調べる手間も時間も省くことができます。
また、悪徳業者に引っかかるといったリスクも少なくなるので、初心者のかたはもちろん、何度も現金化業者を利用するかたであっても、初めて利用する業者である場合、必ず現金化比較サイトを利用しましょう。
 メディア編集部
メディア編集部
現金化比較サイトを利用することで時間や手間が省けるだけでなく、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
実際に使った体験が見られる
比較サイトの中には実際に業者を利用した人のリアルな体験談をのぞくこともできますよね。
とくに、現金化初心者にとっては流れがつかみやすいですし、ある程度不安を取り除く材料ともなります。
だれかが気になる業者を使って現金化して問題が無ければ、「ああ、ここで利用したら問題なく現金化できそうだなあ」と思いますよね。
比較サイトの中には、口コミや体験談をピックアップしているものがたくさんあります。
 メディア編集部
メディア編集部
気になる特定の業者を利用した人のリアルな感想がわかるのは心強い「素材」となるでしょう。
クレジットカード現金化比較サイトの注意点

クレジットカード現金化を利用する前には、必ず現金化の比較サイトをチェックするべきだといえます。
「そんなことを言われる前に現金化業者の比較サイトなんていくつも見てるよ」と言われるかもしれませんが、比較サイトを利用する際にはこんな注意点があることも覚えておきましょう。
- 報酬を支払ってランキングづけしている
- 業者が自作自演の口コミを投稿している
 メディア編集部
メディア編集部
いずれもよくあるケースなのですが、詳しく内容をチェックしていきましょう。
報酬を支払ってランキングづけしている
現金化比較サイトをいくつか見てみると、「本当?」と思うことが必ずあるはずです。
なぜなら、一般的には悪徳業者とはいかないまでも、あまり評判の良くない(換金率があまり良くなかったり、接客が良くない)業者が人気やおすすめランキングのトップに踊り出ているため。多くの人が、「わざとランキングトップに入れてない?」と思いますよね。
ハッキリ言うと、わざとです。現金化業者を利用して利用した現金化業者に関する良い口コミやランキングサイトを書くことで報酬を得る人がいます。
とくに良い業者でなくても、良いと比較サイトで書けば利用者は増えますよね。集客効果を見込んでの報酬を得たサイトも多いので、十分に気をつけましょう。
 メディア編集部
メディア編集部
いくつか比較サイトをチェックした上で、特に気になる業者を数個ピックアップしてさらに細かく調べると失敗を防げます。
安全にクレジットカード現金化をするための3つのポイント

正直な所、クレジットカード現金化はリスキーな行為です。そんなリスキーな行為を安全に行うための知識を、まずは身につけましょう。
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
それでは、細かくそれぞれのポイントをチェックしていきましょう。
クレジットカード現金化をしっかりと理解する
クレジットカード現金化は違法ではありませんが、極めてグレーゾーンとなる行為です。クレジットカード現金化業者は貸金業ではないので、貸金業の許可を受けている業者ほとんどありません。
しかし、現金化業者が摘発されたケースはあり、その場合貸金業法違反で捕まっていることがほとんどなのです。
つまり、現金化業者は貸金業として扱われているケースがあり、それを許可なく行っている現金化業者はやはりグレーと言えるでしょう。
また、そもそもクレジットカード現金化はカード会社がカード規約で禁止している行為ですから、バレた場合、カード利用停止のリスクだけでなく、カードをはく奪、強制退会させられて残債を一括返済することになります。
カード会社にバレなくても、クレジットカード現金化は非常に手数料が高く、何度も続けていると借金地獄に陥る可能性は高くなります。
返済することができなくなり、自己破産したくてもできないことなど、リスクが高い行為であることを理解しておきましょう。
ここがポイント!
クレジットカード現金化を安全に行うためには、少しでも条件の良い優良現金化業者を探すことはもちろん、計画的に返済できる範囲内で利用することをおすすめします。
現金化業者選びを徹底的に行う
最初にお伝えしておくと、現金化業者の8割以上が悪徳業者だと言われています。つまり、優良業者はほとんどないということです。
そのため、「これでいいや」と、適当に現金化業者を選んでしまうと大きな損をしたり、詐欺の被害に遭うこともありますので、現金化業者は徹底しないといけません。
現金化業者にとって、有利な口コミしか載せていないようなサイトに騙されたりはしないでください。
 メディア編集部
メディア編集部
優良業者の選び方は後程詳しくご紹介するので、そちらもぜひチェックしてくださいね。
換金率相場を把握する
クレジットカード現金化業者のホームページに記載されている換金率は絶対に信じてはいけません。
なぜなら、掲載されている換金率はあくまでも「最大換金率」であり、実際の換金率(入金額)と異なるからです。
記載されている換金率から様々な手数料を引かれるので、実際の換金率の平均値は75%前後が相場となっています。
 メディア編集部
メディア編集部
90%以上の換金率で現金化してくれる現金化業者はないと言っても間違いではありません。
このことをあらかじめ押さえておかないと、必ず「あれ?なんでこんなに入金額が少ないの?詐欺じゃないか!」と、思うでしょう。
現金化業者も利益が出なければ仕事になりませんから、記載されている換金率を適用していたら商売として成り立たないのです。
一般的に、優良業者と言われている現金化業者の換金率は80%以上です。換金率の相場を理解した上でクレジットカード現金化を利用しなければ失敗につながるので、この点もしっかりと押さえておきましょう。
クレジットカード現金化のよくある質問
- クレジットカードが利用停止になるって聞いたんですが本当ですか?
- 現金化を目的としたクレジットカードの利用は、規約に違反をしている行為です。不正利用が疑われた場合には、予告なしに利用停止処置が取られる場合があります。
ただ、現金化業者では不自然が履歴が残らないように対策しており、カードトラブルを起こさずに安全な取り引きが可能です。
- クレジットカード現金化でも審査はありますか?
- クレジットカード現金化は借り入れとは異なる取り引きのため、手続きの際に返済能力を審査する必要はなく、収入や就業状況の確認も行われません。
- よく見る「換金率90%以上」って本当でしょうか?ありえますか?
- 現金化の相場としては70%から80%程度。最高換金率が90%を超える場合でも、必ずしもすべての利用者に適用されるとは限りませんし、ここからさまざまな手数料を差し引かれ、実質入金される額が減る場合がほとんどです。
取り引きの際には、必ず正確な振り込み金額を把握しましょう。
- クレジットカード現金化は違法ですか?
- 現在のところ、クレジットカード現金化そのものを取り締まる法律がありませんので、違法ではないと言えます。
ただし、クレジットカード本来の利用方法からは逸脱することから、手続きをしても捕まることはありませんが、グレーゾーンという位置づけです。
- クレジットカード現金化で必要な書類ってありますか?
- クレジットカードが本人名義のものか確認するため、身分証明書が必要です。基本的に、免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものが求められます。
顔写真付きのものがなければ、複数種類の身元証明書類が必要な場合があるため、各現金化業者の指示に従いましょう。
- クレジットカード現金化は分割・リボも可能ですか?
- 通常のショッピングと同様の手続きとなるため、一括払い以外にも分割払いやリボ払いへの切り替えに対応しています。
まとまった金額を現金化した時にも、無理のない支払いが可能です。
- 自分名義じゃないクレジットカードでも現金化はできますか?
- 不正利用防止のため、ごく一部の現金化業者を除いて、ほとんどの現金化業者で他人名義のクレジットカードでは申し込み不可となっています。自分名義ではない家族カードでも同様です。
- クレジットカード現金化は家族や知人、会社にバレますか?
- ネット上の手続きと電話確認のみで対応できるため、誰にもバレずに手続きできます。審査不要ですので勤め先への連絡も行われませんし、カード履歴にも業者名が残らないなど、現金化利用がわからないように配慮されています。
- クレジットカードを悪用されないでしょうか?
- これまでに情報流出トラブルがない、個人情報の保護を徹底している優良業者を選んで申し込めば安全です。
しかし、中には入手した情報の悪用をする詐欺業者も紛れています。取り引き時にクレジットカードの写真、特にセキュリティコードがわかるものを要求してくる業者には注意しましょう。
- クレジットカードの種類で換金率は変わるのでしょうか?
- 換金率がどのように適用されるのかは、現金化業者によって基準が異なります。ただ、各ブランドによって決済手数料が異なるため、換金率から差し引かれる金額の違いによって、入金額に差が出る場合があります。
- 個人情報を送るのに抵抗があるんですが・・
- 利用するクレジットカードが本人名義のものであるか、不正利用防止の観点からはもちろん、買取方式による手続きの場合には、古物営業法により本人確認が義務付けられています。安全な取り引きのために必要な手続きです。
- クレジットカード現金化の方法ってどうやっているんでしょうか?
- クレジットカードで購入した商品を買い取ってもらう「買取方式」と、商品についてくる特典として現金キャッシュバックを受ける「キャッシュバック方式」などが一般的です。
- クレジットカード現金化をすると利息は発生しますか?
- 借り入れではなく、通常の買いもの同様にショッピング枠を利用した分は後日、カード会社が指定する日に口座から引き落とされるかたちで支払うことになるため、利息は発生しません。
ただし、分割やリボ払いを選択した場合には、別途手数料が発生します。
- クレジットカード現金化をするメリットはありますか?
- 信用情報に借り入れの履歴が残りませんし、返済能力を問われないため審査不要。無職で収入がないかたでも、クレジットカードに残高さえあれば申し込むことができ、即日換金が可能なのが魅力です。
- クレジットカード現金化は、高い商品を買って買取店で売った方がお得でしょうか?
- 場合によっては、現金化業者を利用するよりも高い換金率で現金化できます。ただし、現金を手にするまでに手間も時間もかかりますし、換金性の高い商品を大量に、または頻繁に購入していると不正利用検知にかかりやすくなり、現金化目的でのカード使用を疑われやすくなるため注意が必要です。
- クレジットカード現金化にも大手や老舗ってあるんですか?
- 10年以上営業を続けている老舗や法人運営の大手業者もあり、現金化業者の会社概要から実績を調べられます。運営元が実態が明確な現金化業者は信頼性があり、多くのかたが利用していることから、口コミや評判を調べるとよく名前が挙げられているのも特徴です。
- クレジットカード現金化はいつ現金が振り込まれますか?
- 即日プランであれば平均して30分程度のところが多くなっていますが、各現金化業者ごとに対応が異なります。最短数分というスピード対応を謳っている業者であっても混雑時には遅れが生じますので、申し込みの際にスタッフに入金までにかかる時間を確認しておくと安心です。
- 店舗が無いクレジットカード現金化業者は悪徳ですか?
- 店舗維持費がかからず、人件費も節約できることから、その分換金率アップというかたちで利用者に還元しているのがネット業者利用のメリットです。
昨今ではこちらが主流ですし、会社概要を明示して問題なく営業している優良業者も多数あります。実店舗がないからといって悪質業者であるとは限りません。
- クレジットカード現金化はサラ金や消費者金融がやってるって聞いたんですが本当ですか?
- クレジットカード現金化は貸金行為とは明確に異なりますので、サラ金や消費者金融業者が営業をしているということはありません。現金化業者が貸金を行うことは、法律違反となります。
- クレジットカード現金化の申し込みはどうしたら良いでしょうか?
- 現金化業者のHPにある申し込みフォームやメールに必要事項を記入して送信するか、受付対応時間内に直接電話をかけて詳しい相談をすることが可能です。業者によってはLINEからでも申し込みを受け付けています。
- 消費者金融ブラックでもクレジットカード現金化はできますか?
- 信用情報に問題があり、これ以上の借り入れが困難なかたでも、残高のある本人名義のクレジットカードを所持していれば現金化手続きができます。
ただし、現金化した分は後日支払いが必要になるため、計画に利用しましょう。
- クレジットカード現金化って手数料は発生しますか?
- 消費税や振り込み手数料や決済手数料、商品発送の際の郵送料などいくつか種類がありますが、現金化業者によって差し引かれる手数料が異なります。
全て換金率に含まれている場合もありますし、手数料無料としている業者もありさまざまです。
- クレジットカード現金化は土日祝祭日も対応してくれますか?
- 365日年中無休で対応している現金化業者が多く、そういったところに申し込めば土日祝祭日も平日と変わらない対応となっています。
ただ、振り込み指定先の銀行が休みの場合には入金額の反映が翌営業日以降となりますので、24時間対応のネット銀行やモアタイムシステムに参入している銀行を利用するのがおすすめです。
クレジットカード現金化優良店を利用しよう!

現金化業者のほとんどが悪徳業者といっても良いほど、優良業者は少ないです。
そのため、クレジットカード現金化を行う際には必ずクレジットカード現金化に対する知識を得た上で利用することはもちろん、優良業者を利用することが重要となります。
優良業者を選んでクレジットカード現金化をすれば安全に、そして、悪徳業者を利用して詐欺に遭ったり損するようなことはありません。
 メディア編集部
メディア編集部
上記でご紹介した優良店ランキングを参考にして失敗のないクレジットカード現金化を行ってください。
ただし、クレジットカード現金化は違法でなくともカード会社との規約違反にあたり、バレたら大きなペナルティがあることを理解し、自己責任の上で利用しましょう。
 審査不要
審査不要 最短5分の超スピード対応
最短5分の超スピード対応 最大99.5%
最大99.5%
 審査不要
審査不要 最短5分の超スピード対応
最短5分の超スピード対応 最大99.5%
最大99.5%
 メディア編集部
メディア編集部

 メディア編集部
メディア編集部















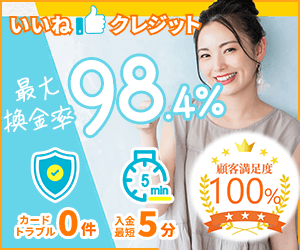























































































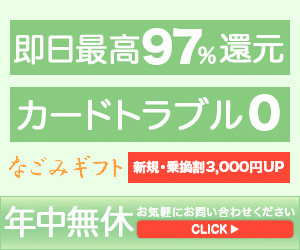












 メディア編集部
メディア編集部

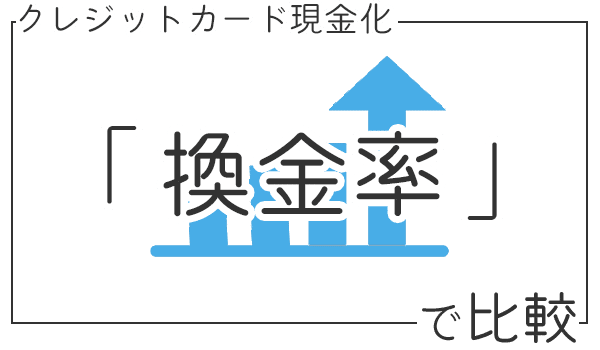
 メディア編集部
メディア編集部

 いますぐクレジット
いますぐクレジット
 スピードペイ
スピードペイ
 ゼロスタイル
ゼロスタイル
 メディア編集部
メディア編集部

 現金化ベスト
現金化ベスト
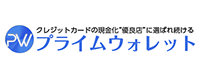 プライムウォレット
プライムウォレット
 スピードペイ
スピードペイ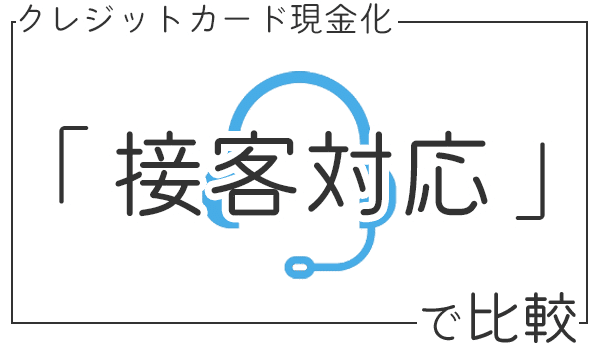
 メディア編集部
メディア編集部

 GENKINKA ITORI
GENKINKA ITORI
 タイムリー
タイムリー
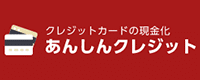 あんしんクレジット
あんしんクレジット
 メディア編集部
メディア編集部

 現金化ベスト
現金化ベスト
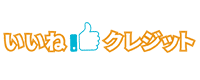 いいねクレジット
いいねクレジット
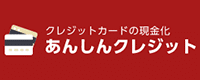 あんしんクレジット
あんしんクレジット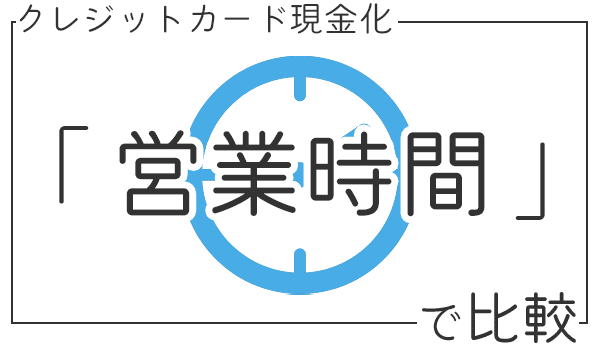
 メディア編集部
メディア編集部

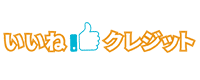 いいねクレジット
いいねクレジット
 GENKINKA ITORI
GENKINKA ITORI
 タイムリー
タイムリー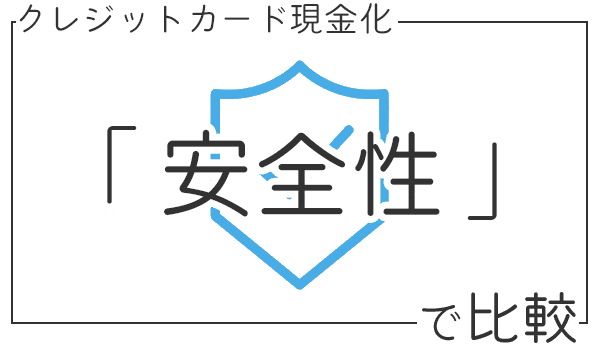
 メディア編集部
メディア編集部

 どんなときも。クレジット
どんなときも。クレジット
 かんたんキャッシュ
かんたんキャッシュ
 88キャッシュ
88キャッシュ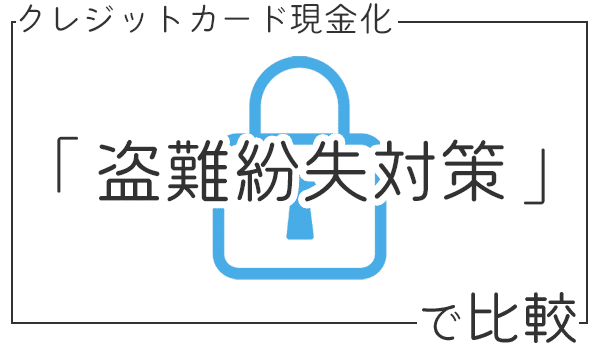
 メディア編集部
メディア編集部

 どんなときも。クレジット
どんなときも。クレジット
 ゼロスタイル
ゼロスタイル
 インパクト
インパクト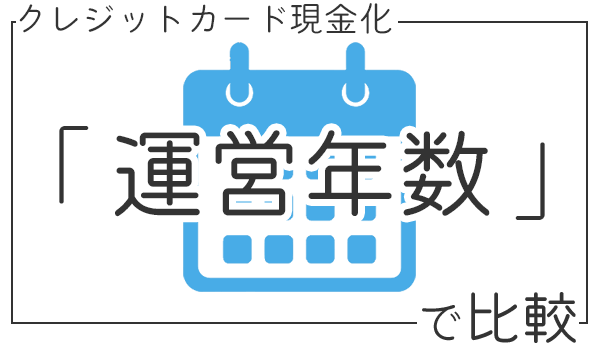
 メディア編集部
メディア編集部

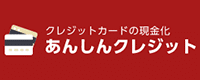 あんしんクレジット
あんしんクレジット
 セーフティーサポート
セーフティーサポート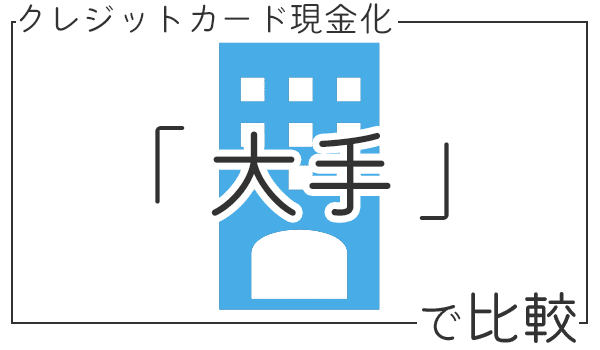
 メディア編集部
メディア編集部

 ブリッジ
ブリッジ
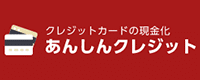 あんしんクレジット
あんしんクレジット
 GENKINKA ITORI
GENKINKA ITORI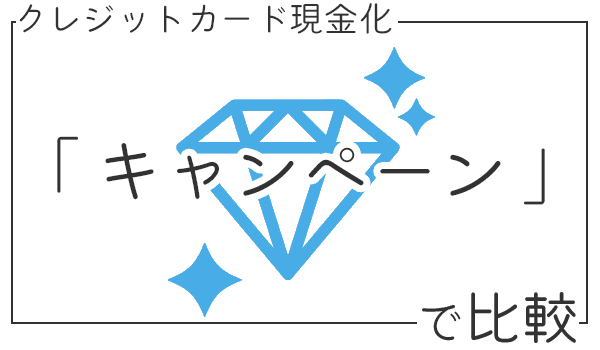
 メディア編集部
メディア編集部

 ブリッジ
ブリッジ
 タイムリー
タイムリー
 インパクト
インパクト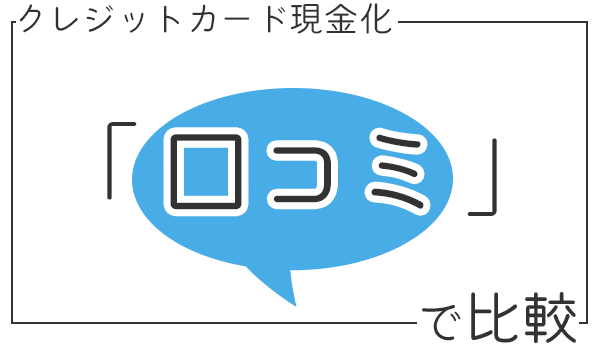
 メディア編集部
メディア編集部

 いますぐクレジット
いますぐクレジット
 スピードペイ
スピードペイ
 ブリッジ
ブリッジ タイムリー
タイムリー ブリッジ
ブリッジ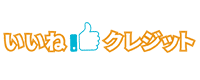 いいねクレジット
いいねクレジット GENKINKA ITORI
GENKINKA ITORI 現金化ベスト
現金化ベスト ソニックマネー
ソニックマネー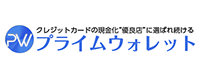 プライムウォレット
プライムウォレット ラストチェンジ
ラストチェンジ トラストキャッシュ
トラストキャッシュ オレンジチケット
オレンジチケット スピードペイ
スピードペイ ゼロスタイル
ゼロスタイル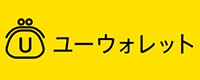 ユーウォレット
ユーウォレット パーフェクトギフト
パーフェクトギフト どんなときも。クレジット
どんなときも。クレジット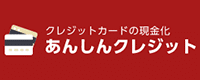 あんしんクレジット
あんしんクレジット インパクト
インパクト スマイルギフト
スマイルギフト キャッシュライン
キャッシュライン かんたんキャッシュ
かんたんキャッシュ ひまわりギフト
ひまわりギフト セーフティーサポート
セーフティーサポート 88キャッシュ
88キャッシュ
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部

 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部

 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部

 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部
 メディア編集部
メディア編集部

 メディア編集部
メディア編集部
